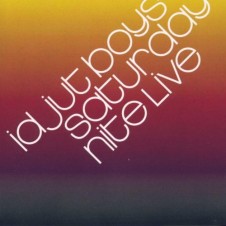MasteredレコメンドDJへのインタビューとエクスクルーシヴ・ミックスを紹介する「Mastered Mix Archives」。今回登場するのは、DJハーヴィーとともに、長年に渡ってオルタナティヴなディスコ/ハウスを日本に紹介してきたイギリスの人気DJデュオ、イジャット・ボーイズ。
コンラッド・マクダネルとダン・テイラーからなる彼らは、1993年のファースト・シングル「Idjut Boys EP」リリースから今年で目出度く20周年を迎え、日本各地を回るアニヴァーサリー・ツアーを大盛況のうちに終えたばかり。その記念すべきタイミングで、彼らの長きに渡るキャリアを振り返るべく、ロング・インタビューを敢行。併せて、いくつかのライヴDJミックスを除いて、オンラインではほとんど提供していないというDJミックスの制作を依頼した。じっくり楽しめそうな、リスニング・オリエンテッドなレア音源とともに、楽しい冬休みをお過ごしください。
※ミックス音源はこちら!(ストリーミングのみ)
1人でDJすることもたまにあって、それはそれで楽しいんだけど、2人の時とは違うんだよな。(ダン)
そうそう、俺たちはやっぱり一緒にやるのが一番いいんだよ。(コンラッド)
— まず、スタジオの引っ越しで忙しいなか、今回、DJミックスを作ってくれたそうで。
コンラッド(写真右):全然問題ないよ。他でもない日本のリスナーのためだからね。そうじゃなきゃ、きっとやってなかっただろうな。
— ありがとうございます。そして、イジャット・ボーイズの最初のシングル「Idjut Boys EP」リリースから20周年を迎えたということで、おめでとうございます。
コンラッド:ありがとう。とはいっても、あまりに昔のことすぎてはっきり覚えてないから、今日、この日から20年ということにさせてもらうよ(笑)。
— 最初のギグは、DJハーヴィーのパーティ、モイストのアフターアワーズだったそうですね。

Various Artists『More or Less』
イジャット・ボーイズが主宰するU-Starレコーズが2000年にリリースしたレーベル・ショウケースとなるコンピレーション&ミックスCD。デビュー20周年を記念して、限定300枚で日本のみリリースされたばかり。
ダン(写真左):そうだね。場所は俺たちの自宅。人数はリビングに収まるぐらいだったかな。
コンラッド:確か、(DJ用のダイレクトドライブではない)ベルトドライブのターンテーブルを2台使ったんだよな。
— 当初からDJデュオとして活動していくつもりだったんですか?
ダン:友達だったから一緒にDJをやったんだけど、そういうつもりはなかったんだよね。
コンラッド:俺たちのスタイルは時間をかけてだんだん発展していったんだ。2人でブースに入って、お互いにレコードをプレイし合うスタイルの受けがいいってことに気づいたのも10年ぐらい前だったりするし。今となってはそのスタイル以外は考えられないけど、何か狙いがあってバック・トゥ・バックのスタイルになったんじゃなくて、それもまた偶然なんだよ。
ダン:1人でDJすることもたまにあって、それはそれで楽しいんだけど、2人の時とは違うんだよな。
コンラッド:そうそう、俺たちはやっぱり一緒にやるのが一番いいんだよ。
— 2人は知り合ってから、それこそ、25年以上経つわけですけど、お互いどういう部分が合うんだと思いますか?
ダン:人間だからお互いにイラッっと来ることがないわけじゃないけど、何か問題があったら、早いうちにコミュニケーション取るようにしているし。
コンラッド:ダンは俺の兄弟というか、家族みたいなもんだからね。家族にも仲がいい時、悪い時があるように、俺たちの関係は昨日今日のものじゃないからな。そういう相手に巡り会えたのは幸運だったね。ダンにイライラする時は、それ以上に自分に対してイラつくよね。そういう状況にしてしまった自分に対して。
ダン:わかるわかる。俺は完璧な人間じゃないし(笑)。コンラッドもいいやつだけどパーフェクトではないからね(笑)。
— 2人が出会った80年代末のイギリスでレイヴ・カルチャーが爆発的に広まった背景には、長く続いた不景気がありましたよね。
ダン:それは間違いなく理由の一つだね。人々が搾取されていたというか、社会に不満を持っていたという状況がレイヴというムーヴメントを加速させたのは間違いないな。結果的にその後、ダンス・ミュージックは大きな産業になったけど、初めの頃は誰もこうなるなんて考えてなかったと思うよ。音楽的にもその頃に色んなジャンルが生まれて、クラブやレーベルも沢山出来た。60年代のイギリスで、スウィンギン・シックスティーズと呼ばれるムーヴメント以降、パンクの次に起こった文化的な革命がアシッドハウスだよ。
コンラッド:個人的にはアシッドハウスの方が60年代に起こったことよりも強力だったんじゃないかと思うね。パンクはイギリス国民に活力を与えたけど、アシッドハウスも同じような役割を果たしたと思う。アシッドハウスがもたらしたのはクリエイティヴな精神と一体感。クリエイティヴィティは今でもあるけど、あの一体感は失われてしまった気がするね。そして、何より重要なのは、アシッドハウスは商業的なムーヴメントではなく、完全にアンダーグラウンドものだったということ。その点も今とは違うよね。みんなが知っているから、今の状況下でダンス・ミュージックはアンダーグラウンドになりようがない。もっとも、今の俺は20歳じゃないから、何が若者の文化的な原動力なのか分からないし、レイヴ以降の変化はポジティヴに捉えているよ。今のダンス・ミュージックはアンダーグラウンドなものではなくとも、そうした変化がなければ、自分が今こうして音楽で飯を食ってることもなかっただろうし、昔の方が良かったとは思わないな。
— 長く音楽を続けてきて、2人を変えた出来事というのは?
ダン:(ハーヴィーやラブンタグのトーマスらが参加していた伝説のサウンドシステム)TONKAは間違いなくそうだね。それから、90年代中期にアメリカの西海岸に行ったことも大きかった。自分たちでU-Starっていうレーベルを立ち上げてから、何度も行ったんだけど、あれはすごく刺激的だった。
コンラッド:なかでもウィキッド・クルー、ガース、イェノ、トーマス、マーキーの4人は、いい場所、いいタイミングに居合わせたサンフランシスコの草分け的な存在だね。
コンラッド:そして、4人ともイギリス人なんだよな。
ダン:変な話だよね(笑)。
コンラッド:そして、90年代後半から日本に来るようになったこと。
ダン:それから俺たちがレーベルを始めたのが、ちょうどみんなレコードを買ってる時期だったということ。これはラッキーだったな。だって、リリースすれば、1週間で買ってくれる人が5,000人ぐらいいたからね。
コンラッド:U-Starが一番売れてる時は、「Quakerman EP」が確か1週間で11,000枚とか。今だったら普通にチャートヒットになってるぐらいのセールスがあったんだけど、当時、それは特別なことじゃなかったからね。
— 今とは別世界の話ですね。
ダン:100パーセント別世界だね。
コンラッド:あとさ、俺たちはプレイしているレコードのことを訊かれれば、いつでも隠さないで教えるんだけど、当時はタイトルが分かってもそれを見つけるまでに時間がかかった。でも、今はネットですぐ買えるだろ。写真に撮って、Discogsで検索すればいいから、DJに話しかける必要すらない。
ダン:つい最近も実際にあったんだよ。DJ中に知り合いが「写真撮ってもいい?」って言うから「いいよ」って答えたら、すぐブースに戻って来て「買ったよ!ありがとう!」って(笑)。あと、マンチェスターの(今はなき人気パーティ)Electric ChairでDJした時だったと思うんだけどね、客の誰かがレコード箱からちょっと見えてるレコードの写真を撮って、(ディスコ、ハウスの有名サイト)DJ Historyの掲示板で「これ、何のレコードか分かる人いる?」っていうトピックを立てたら、すごい盛り上がっちゃって。しかも、ほとんど何の写真か分からないのに「これはRare Earthの『Ma』だよ」って当てた人がいたり(笑)、「あの2人は人生かけてレコード掘ってるのにお前らはなんだ!知りたかったら直接聞けよ」って説教するやつまで出て来たりしてさ(笑)。なんて言うか、とにかくすごいことになったんだよね。
— はははは。話を戻すんですけど、アシッド・ハウスが下火になってから、2人はUSハウスやディスコに傾倒していったんですよね?
ダン:そう。それでディスコをかけてると「こんなゲイの音楽じゃなくてハウスをかけてくれ」って言われることはあったりして(笑)。でも、例えば、フランキー・ナックルズのDef Mixみたいなドープなハウスもルーツや編曲の仕方、組み立て方、全体的な美的感覚の根っこにあるのはディスコなんだよね。
コンラッド:U-Starからリリースしてた作品もライブ・ミュージシャンをフィーチャーしたハウストラックだったけど、機械じゃなく、ライヴ・インストゥルメンツを用いるのが自分たちにとってのディスコだったから、同じやり方でやっただけだし。
ダン:そうそう。当時は「なんでハウスなのに生楽器を使うんだ?」って、よく言われたよな。
コンラッド:俺たちはディスコがハウスのルーツだと思ってたからね。行ったことはないけど、Loftでかかってるハウスもそういうことだろ。
— ハウストラックに生楽器をフィーチャーするスタイルは、のちにU-STAR、そして、UKハウスのオリジナリティに繋がってきましたよね。

Meanderthals『Desire Lines』
LindstromやPrins Thomas、Todd Terjeを輩出したノルウェー・シーンにあってリスペクトを集めるベテランDJ、プロデューサー、リューネ・リンドバークとイジャット・ボーイズがコラボレーションを行った2009年作。
コンラッド:まず第一に、誰かと同じような曲を作ったんじゃ意味がないと思ってた。「何で、みんなと同じことをしないといけないんだ?」って感じで、この20年間で同じ曲を作ったことは一度もない。自分たちに曲作りの知識がなかったことも、オリジナリティに繋がった理由の一つだな。
ダン:そう、俺たちの曲作りは計画的なものじゃなく、感覚的なものだからね。そして、スタジオでは、ルールがないのがルールというか、ミキシングボードで音を出し入れする以外は何も決まってないんだ。だから、次に何が起こるか、自分たちでも分からないだよ。
コンラッド:そう、ミキサーが俺たちの楽器なんだ。ピンク・フロイドの『The Dark Side of the Moon』の制作過程を追ったドキュメンタリーがあるんだけど、そのミックスが演奏と同じぐらいクリエイティヴなんだよ。自分の崇拝する人たちが、自分と同じことをやってたんだってことが分かって、そのドキュメンタリーはすごく励みになったね。バハマのコンパスポイント・スタジオで作られてた音楽やジャマイカのダブも、全部ミキシングボードを使って作られたものだろ? 俺たちも同じようにミキサーを楽器のように演奏するんだ。
ダン:コンパスポイントといえば、ポール"グルーチョ"スマイクルがミックスしたウォーリー・バダルーやボブ・マーリーの曲を聴くと、そうした作品がライブミックスだってことが分かる。あれはライブだからこその良さ、そういう時代の美学があった作品なんだよな。
コンラッド:ただし、今ではベテランのプロデューサーでもPCに移行する人が増えて、俺たちみたいなやり方で作品を作る人間は少なくなったね。でも、彼らは彼らのやり方ですごい作品を作ってるから、それはそれでいいんだ。若い人たちにとっても、マウスがミキシングボードの代わりだろうしね。でも俺とダンは、そのやり方だと音楽と繋がってる感じがしないんだよね。だから、俺たちは一切プログラミングを用いずに、全てを本能の趣くままにやるんだ。一日中ミックスしたり、何日もかかって組み立てたものを全部ぶっ壊したりね。そうすることによって、作品にマジックが生まれるんだよ。
ダン:そう。それがミキシングボードを使い続けてる、俺たちなりの理由なんだ。
コンラッド:そして、音楽と繋がってるように感じられるから、同じようにDJする時にもエフェクトを使うんだよ。
— そうしたミキシングはレゲエの影響も大きいんでしょうか?
ダン:レゲエのパーティーにはあんまり行ったことないんだよね。もちろん、レゲエのレコードは大好きでよく買うし、2フロアあるクラブの片方のフロアがレゲエだったり、ラジオで聴いたりはしてたけどね。
コンラッド:コンラッド:ただ影響はあると思うね。俺自身はジャー・シャカよりハーヴィーのパーティーによく行ってたけど、あのシステムでレゲエを聴いた経験は無意識のうちにでも影響されてると思う。それだけじゃなく、ロック、レゲエ、スカ、ディスコ、モリッシーみたいなインディ・ミュージックにレッド・ツェッペリン……そういうあらゆる音楽から受けた影響が俺たちの音楽には入ってる。むしろ、曲を作る時はいつもアイディアが多すぎて削らなきゃいけないぐらいさ。
ダン:ダブの話に戻ると、ツマミをガンガンいじって音を変えていくっていうやり方は、ラリー・ハードとかロン・ハーディーが作ってたシカゴハウスにも通じるものもあるよ。
コンラッド:それにジャマイカ人はファンク・ブラザーズがバッキングを務めていたモータウンを聴いて、アメリカのR&Bをやろうとして、レゲエを生み出しただろ? つまり、レゲエはソウルだし、ソウルってことはディスコにも繋がるんだ。そうやって、海を越えることで、音楽はその土地に影響をもたらしてきたんだよ。テクノだって、デトロイトのやつらがデペッシュ・モードやユーリズミックスみたいになりたくて始めて、アウトプットの段階で全く異なるものになったわけだし、そうやって音楽は進化していくんだ。
— 同じように、90年代中後期は、Nuphonicだったり、2人が始めたNoidやDiscfunctionといったレーベルを中心に、ニューハウスと呼ばれるイギリス固有のハウス・ミュージックを生み出すことになりましたもんね。
コンラッド:あの当時、UKの音楽シーンはすごく盛り上がってたよね。ブームには移り変わりがあって、今はドイツがちょうどそんな感じかな。当時の俺たちはその渦中にいたから、何が要因で盛り上がったのかよく分からないけど、そういうサイクルは常にあるよね。あとは金かな。金が絡むとシーンが変わるのは間違いないね。今のヨーロッパのシーン、南アメリカ、北米のEDM、どこもとんでもない額の金が絡んでる。一昔前のロックバンドに投下されてた金が、今はDJに注ぎ込まれてるんだ。DJ一人で5万人の客を呼べて、その客が50ドルとか60ドルのチケットを払って遊びに来るんだから、状況が変わるのは当然だよな。日本だって10年前と今じゃ全然違うだろ? 「渋谷にあんなに沢山あったレコード・ショップはどこに行っちまったんだ!」って話だし。
ダン:俺たちは年に2回ぐらい来るだけなのに、それでもこの変わりようにはびっくりしているくらいだからね。でも、音楽を聴く人がいなくなったわけじゃない。そこは変わらないからね。
コンラッド:それに俺たちはDJや曲作りはキャリアの一貫として、やってるわけじゃない。好きだから続けてるんだ。成功を金ではかる人もいるだろうけど、自分にとってはそうじゃない。もし金のためにやってるんだったら、俺たちは相当なバカだよ。
— そして、90年代後半、2人はノルウェーや日本で頻繁にDJをするようになりましたよね。

Idjut Boys『Cellar Door』
長いキャリアで初となる2011年リリースのファースト・スタジオ・アルバム。ミキシングボードを楽器代わりに一流プレイヤーのセッションをサイケデリックかつチルアウトなサウンドスケープへと昇華させた美しい一枚だ。
コンラッド:ノルウェーはもう数えきれないぐらい行ったね。ベルギーやイタリア、スペイン……他のヨーロッパの国にも同じぐらい行ってたんだけど、ノルウェーは特別楽しかった。すごいフィットしたんだよね。DJもめちゃくちゃハマったし、何か通じるところがあったんだよな。ノルウェーのいいプロデューサーを5人挙げろって言われたら、10人は答えられるし、あんな小さい国に俺たちと同じ音楽を好きなやつらがあんなに沢山いるのは、マジで信じがたいことだったよ。
ダン:初めはあんなことになるなんて想像もしなかったね。ノルウェーには色んな土地に色んなプロデューサーがいるんだけど、みんな競争心が全然ないんだ。本当に仲が良くて、「俺の友達の新作聴いたか?」とか「あいつ、いいDJだから一緒にやった方がいいよ」とかお互い言い合ってる。音楽はもちろんだけど、人間的にもすごくいいやつらなんだよな。
— 日本の印象はいかがですか?
ダン:初めて来た時も、もっとよく知るようになった今でも、文化的にはまったく違うなって思うよ。でも人間的にはすごい合うんだよね。クラブには世界的に見ても、ベストな機材が揃ってるし、お客さんも最高だ。今も昔も、日本はアメリカのダンス・カルチャーを取り入れて独自に発展させて来た国という印象があって、例えば、Yellowなんかはニューヨーク的な流れを汲んだクラブだっただろ。それから、音楽の聴き方にしてもファッションにしても、日本はディテールにこだわる文化っていう気がするね。
— イジャット・ボーイズと日本の相性の良さはどの辺にあるんだと思います?
コンラッド:分かんねえな。もし具体的な理由があれば知りたいね。ほかの国へ行った時に使えそうだろ(笑)。ただ、いつ来ても、日本はやる気にさせてくれるし、何か新しいことをやろうって気にさせてくれる国なんだ。今までかけたことがない曲をプレイしようとか、ここに来るといつもそういうスイッチが入るんだよね。恐らく、お客さんと自分たちの関係がすごくいいから、もっといいものを見せたいと思えるんだろうね。
ダン:いいパーティーをするにはそういう関係が必要だよ。
— 2000年代後半以降、ディスコがまた戻ってきたと言われていますよね。
ダン:どういうサイクルなんだろうね。何かの意志が働いてるのかな。俺たちは意識せずに今まで通りやってるだけだから、変な感じだね。でも、ハーヴィーにしたって、変わらずにずっとやり続けてることにまたみんなが反応するようになったわけだろ。長く音楽を続けるというのは、そういうものなんじゃないかな。
コンラッド:ただ、自分たちにとって、この10年は今までの人生で一番いい時期だったと思うよ。音楽の流行り廃りはあっても、遊びに行って踊りたいって思う人たちがいるのはいつの時代も変わらないのに対して、音楽は変わるよね。変わるべきだとも思う。そんななか、未だに自分たちを受け入れてくれてる人がいるのは本当に嬉しいね。だって、20年も経ってるんだぜ。同じ会社に20年勤めてたら金時計もらえるって(笑)。20年もこんなことやり続けられてるなんて、これ以上なく名誉なことだよ。しかも、これはお世辞じゃなく、日本に来るようになったことが自分たちの20年をより一層特別なものにしてるんだ。
ダン:歳を取るほどにその思いが強くなって、今は感謝の気持ちでいっぱいだよ。
— DJはいつまで続けたいと思ってます?
コンラッド:新しい世代のリスナーに求められて、そこに喜びを感じる限りは引退しないでやり続けるよ。やめる理由がないだろ?
ダン:一方通行じゃ駄目だけど、お互いそう思ってるんだったら決まりでしょ。UKにはアメリカのベテランのDJがよく来るんだけど、例えば、トニー・ハンフリーズのプレイは未だにヤバいんだぜ。俺たちはヘアスタイルとか、どれだけ体を鍛えてるかで勝負してるわけじゃないじゃん?(笑)。トニー・ハンフリーズがそうであるように、スピーカーから出てくるものが全て。それが大丈夫な限りはいけると思うね。
— 最後に今後の予定を教えてください。
コンラッド:来年前半に『Cellar Door』のダブ・アルバムをリリースしようと思ってる。そして、今回、U-Starのレーベル・コンピ『More or Less』を再発したけど、その目的はただ一つ。2014年にU-Starを再始動させることなんだ。新生U-Starからリリースする最初のレコードのタイトルは(1993年に出したファースト・シングル「Idjut Boys EPの続編)「Idjut Boys EP2」にしようと思ってるよ。
— 答えはなんとなく想像が付くんですけど、曲は出来てるんですか?(笑)
コンラッド:当然出来てねえよ(笑)。
ダン:ヤなこと訊くな(笑)。