MasteredレコメンドDJへのインタビューとエクスクルーシヴ・ミックスを紹介する「Mastered Mix Archives」。12回目となる今回登場するのは、池田正典氏です。
英国タイムアウト誌が選ぶ「90年代のパーティトップ10」の4位に選ばれたほか、英国で大成功を収めたパーティ「BLOW UP」のレジデントDJとして、そのキャリアを切り開いた彼は、日本帰国後に大ヒットを記録したミックスCDシリーズ「SPIN OUT」やMansfieldほか様々な名義での作品リリースを通じて、お馴染みのDJ、プロデューサー。
2000年代後半以降の彼は、豊かなパーソナル・アーカイヴからチョイスしたディスコ、ハウス、バレアリックを軸にフリースタイルなプレイを展開していますが、そのルーツが語られる機会はほとんどありませんでした。そこで今回はその謎めいたキャリアを紐解きながら、制作をお願いした夏にぴったりの極上フュージョン・ミックスをお楽しみください。
※ダウンロード版の提供は一週間限定となります。お早めに。
※ダウンロード版の配信は終了しました。
自分は常に次の展開を求める単なる音楽ファンなので、音楽性も変化していくのは自然なことなんですよね。
— 90年代の大半はロンドンにいらっしゃったんですよね?
池田正典(以下池田):そうですね。自分が10代だった80年代から90年代初期のロンドンの音楽は影響力がとにかくデカかったから、とりあえず行ってみよう!と思ったんですよね。で、ふらっとお金貯めてロンドンへ旅行のつもりで行って、そのまま、語学学校を決めた後、学生ビザを取って、向こうで生活を始めたんですよ。当時の自分はレコードのコレクターで、DJはまだ始めてなかったんですけど、ターンテーブルを買って、DJを始めたら、次第にレギュラーが決まるようになっていったんです。
— 当時はどんな音楽を聴いてたんですか?
池田:今と変わらず、幅広く聴いてましたね。日本を出る直前は808ステイトとジェームス・ブラウン……つまり、ハウス、テクノとレア・グルーヴ、アシッド・ジャズが混沌としていたというか。当時のロンドンは、今のようにジャンルが細分化してなかったから、テクノ好きはテクノ好きだけでつるむとかはなく、横のつながりで、色んな音楽好きと遊んでいたんですけど、その後、一緒に住んでいた友達が急に家を出ることになって、家賃の支払いに困ったんですね。そこで、ポートベローの(レコード・ショップ)オネスト・ジョンズの並びで、知り合いがやってたレコード屋の出店の脇を借りて、自分で7インチのファンクをコンパイルしたテープを売り始めたんですよ。その頃、マーケットでテープを売るのが流行ってたんですけど、当時一番人気があったテープ屋のデイヴィッドってやつが僕のテープを気に入ってくれて、「カムデン・マーケットにいるテープ・ブラザーを紹介するぜ!」って。それで紹介されたのがケヴ・ダージとジャズマン・レコーズのジェラルドだったんです。
— いきなり、スゴい話ですねー(笑)。
池田:それでみんなで一緒にDJをやってるうちに、カムデンで「BLOW UP」っていうパーティが始まるんですけど、そのパーティが思いもしなかった大規模なヒットになっちゃって(笑)。全部成り行きというか、単なるラッキーガイですよね。
— 「BLOW UP」について、ここで改めて説明したいんですが。

V.A.『Blow Up presents Exclusive Blend Volume 1』
池田氏がレジデントを務めていたロンドンの人気パーティ「BLOW UP」が1996年にリリースしたファースト・コンピレーション。ライブラリー音源のニュー・ディスカバリーを先駆けるダンストラックを多数収録している。
池田:「BLOW UP」ってパーティは、94年頃に始まったんですけど、形態的には2フロアあって、1フロアは典型的なモッズ、ノーザン・ソウル、当時流行っていたギター・ロックなんかをプレイしていて、もう1フロアは僕がレジデントを担当していたんですけど、そっちはカーミンスキー、ケヴ・ダージ、ジャズマン・ジェラルド、それからセント・エチエンヌのボブ・スタンリー、あと、スロッビング・グリッスルのコミューン出身っていうAdd N to (X)のバリー、ジェントル・ピープルのダギーっていう面子を毎週代わる代わる呼んで、45分交代でプレイしてました。
— 当時、「BLOW UP」はブリット・ポップに代表されるクール・ブリテンの盛り上がりとうまい具合に噛み合っていたという印象があります。あまりに集客が好調で、パーティ会場がカムデンから名門クラブのワグに移ったんですよね。
池田:そうそう。カムデンでやってた時は入れない人が多いときにに50メートルくらいの列になってて、その列にいた子たちがその後、(人気音楽テレビ番組)「TOP OF THE POPS」に出るバンドになったり、面白かったのは、「BLOW UP」って、バンドのツアーDJにかり出されることも多くて、よくプレイしていたのはブラーと(アシッド・ジャズ・グループ)ジェームス・テイラー・カルテットっていう全然違うタイプのツアーだったんですね。で、「ジェイムス・テイラー・カルテットはうちらの方が得意そうだから……」ってことで僕らが担当して、ブラーの方はモッズ・フロア担当に任せたり(笑)。「BLOW UP」自体もイギリス全土を周りながら、ロンドンとブライトンでレギュラーを持っていたし、NME主催のブリティッシュ・アワードのDJも毎年みんなで担当したり、動きもかける音楽もロンドンならではのごちゃまぜな感じですよね。
— プレイしていたのは、ラウンジ・ミュージックってことになるんですか?
池田:いや、ラウンジ・ミュージックのパーティはホントのラウンジでやってたじゃないですか? でも、僕らは、レフトフィールドで踊れるものを掘り出してきてはプレイしていたというか、のちにイタロ・ディスコとしてピック・アップされるハリー・サーマンの「UNDERWATER」もガンガンかけていたし、僕らの間ではそういう音楽を「スペーシー」って呼んでたんですよね。
— 池田さんが精通しているライヴラリー音源にもレフトフィールドかつ踊れるトラックが沢山眠っていますもんね。
池田:そう。だから、僕らのパーティをチェックしに来てたのは、ファンクとかジャズのディーラーが多かったですね。確かにのちにラウンジ・シーンと呼ばれることになるロンドンの源流は僕らであることも確かなんですけど、そういう情報って、日本に入ってくる段階で多少曲がって伝わることって多いじゃないですか? そんな、フランク・シナトラみたいな曲をかけたって、誰も踊るわけないし(笑)、その後、ブームになって、イージー・リスニングで踊ってる様子を見て、なんか全然違うことになってるなって思ってました。
— ジェントル・ピープルにしても、日本に入ってきた時は新しいイージー・リスニングとして扱われていましたけど、彼らのアルバムはリフレックスから出ていたし、音の配置はテクノ以降のものですもんね。

The Gentle People『Soundtracks For Living』
リチャード・D・ジェームス(エイフェックス・ツイン)の主宰するリフレックス・レコーズより、1996年にリリースされたファーストアルバム。
池田:彼らも色んな音楽を聴く人たちで、ファースト・アルバム『Soundtracks For Living』はそういうものを一通り通過した作品だったし、「BLOW UP」でかけてたものにしても、他では聴けないものだったから、みんな、ネタのチェックに来てて、ステレオラブも僕らのDJブースの横で「ノリ、この曲、何なんだ?」ってよく言ってたし、その後のブレイクビーツ・ブームも「BLOW UP」でかけてた曲が結構ネタになっているんですよね。
— 当時、そういうレコードはどういったところで掘っていたんですか?
池田:いや、レコード・ショップの地下にある安売りフロアとかですよ。20円くらいのレコードを1日何十枚っていう単位で当てずっぽうで買って、1曲当たったらいいやっていう掘り方ですよね。自分のルーツはレア・グルーヴっていうことになるんですけど、どんどん探すものもなくなっていきつつ、お金を出せば、どんなレコードも買えるっていう状況が面白くなくて、オールジャンルの安いレコードから新しい発見する方向に向かっていったというか、レア・グルーヴを一番最初に掘り尽くした人たちの次の段階ってことですよね。そういう友達の中には、カーミンスキー・エクスペリエンスのマーティンって友達がいて、彼はBBCのサウンド・ライヴラリーで働いていたので、気になるものは全部そこでチェックしたりとか(笑)。彼らはアシッド・ジャズの時代にヴァイブス・アライヴってユニットをやってたんですけど、A面はジャズネタのトラックなのに、裏面はアンビエントになってたり、そういう普通じゃないことをやってた人がまわりに沢山がいて(笑)。
— (笑)池田さん自身もロンドンのレコード・ショップ、ソウル・ジャズ・レコーズで店員として働いていたんですよね?
池田:働いていたっていうか……まぁ、働いていたんですけど(笑)、当時、僕は店の近所に住んでいて、友達との待ち合わせ場所に使ったり、店にたむろしていたら、ある日、店のオーナーに呼ばれて、「お前、毎日来てるから店で働けば?」って言われて(笑)。スタッフが足りない時の非常勤要員として働いていたので、気になるジャズ盤はそこで全部チェックさせてもらってました。
— ソウル・ジャズの近くに住んでいたってことは、ソーホー?
池田:そう。ジェントル・ピープルの子たちとフラットをシェアしてたんですよ。
— 少々脱線しますけど、ジェントル・ピープルって、たしか、パンク・バンドのクラッシュと関係があったような……
池田:当時は本人の希望でその情報は公表されてなかったんだけど、セーラっていう女の子のメンバーがクラッシュのベース、ポール・シムノンの妹なんですよね。
— 面白いなー。人脈が入り乱れてますね。
池田:友達には恵まれていたとは思いますね。そうやって教えられたり教えたりしつつ、自分もレコードのディーラーみたいなこともやってて。というのも、当時の発見は、世の中的にもニュー・ディスカバリーだったし、ネットのアーカイヴもガイド本もない時代だったから、ひたすら掘るしかなかったし、レコードの値段が決まってなくて、それを買うDJも「いくらでも払うからさー」って感じだったんですね。だから、自分で値段をつけたレコードを売ったり、予備のレコードを交換したりしながら生活してましたよ。今でこそ、ネットで全て値段が付いちゃってますけど、当時はホント原始的な世界でしたね。
— 一方で、日本に帰ってきてからMansfieldほか、様々な名義での活動が本格化する音楽制作は、いつ頃から始めたんですか?
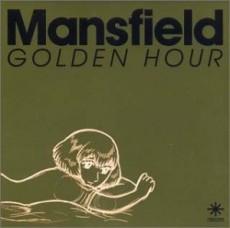
Mansfield『Golden Hour』
UK産のブレイクビーツがメインストリームに押し上げられるなか、ポップスを作ることにクリエイティヴィティを発揮していた池田氏のレコーディング・プロジェクト、Mansfieldが2002年に小西康陽氏のREADYMADE INTERNATIONALよりリリースしたベスト・アルバム。
池田:音楽制作は、ビザを取るために始めたんですよ。というのも、僕は学生ビザで7年くらい住んでいたんですけど、滞在がそれくらい長くなると、さすがにイミグレーションで「これ以上、何を勉強したいわけ?」って突っ込まれるし、滞在を延長しようと思って提出したパスポートが1年くらい返ってこなかったり。DJでは申請は無理。そんな状況だったから、「BLOW UP」とかソウル・ジャズのみんなが弁護士を雇ってくれて、「うちの社員ってことで申請してみたら?」って。でも、イギリスで外国人が必要な人材として認められるためには、多大な年間年収保障が必要で、「さすがにそれは無理だよね」って話から、今度は「アーティストだったら認められるんじゃないか?」って。ただ、僕は楽器も弾けないし、「急にアーティストになれって言われてもなぁ……」って思いつつ、とりあえず、P.P.ロイってやつとカットアップ・コラージュだけで音楽を作り始めたんですよ。そうしたら、リフレックスのリチャード(D・ジェームス)が作ったものを気に入ってくれて、「これを出したい」って話になったんですけど、制作の途中で日本に帰るリミットが来てしまって。だから、P.P.に途中まで作った音源を預けて、「あとはお前が作って自分のアルバムにしたら?」って(笑)。
— はははは。

P.P.Roy『You Can't Help Liking...』
インタビュー中で語られている、池田氏の最初期の共作トラック3曲を収録した、レフトフィールドなブレイクビーツ・クリエイターの1stアルバム。ジェントル・ピープル同様、リチャード・D・ジェームスのリフレックスより2000年にリリースされた。
池田:いやー、全ての話が若気の至りって感じで(笑)。その後、P.P.経由でリフレックスから契約金が振り込まれたんですけど、それから4年後に預けた音源はP.P.のファースト・アルバム(『You Can’t Help Liking…』)としてリリースされたっていう(笑)。
— はははは。大きく捉えて、イギリスと東京の音楽環境、クラブ・カルチャーは何が違うんだと思いますか?
池田:ロンドンはやってることが面白ければ認めてもらえて、どんどんフック・アップされる。だから、いつの時代も新しい才能が突然変異的に現れるのはそういう理由があると思うんですよ。
あと、東京ではまだまだよそ行きな感覚がありますけど、ロンドンではいわゆるクラブ・ピープルみたいなことではなく、普通の人達が仕事を終わって、「一杯飲みにクラブへ行くか!」って感じで、生活のなかに溶け込んでる。それから、ロンドンのクラブに夢があるのは、入場料は全部イベンターに入って、クラブは酒の売り上げで儲けるんですよ。
— 海外のライヴハウスも同じシステムだっていいますよね。

池田 正典(イケダ マサノリ)
キャリアを90年代のイギリスでスタートさせ、ポール・タンキン主催による伝説のパーティ「BLOW UP」のレジデントを務めるなどした後、凱旋帰国を果たした逆輸入系DJ。さまざまなダンスミュージックを自在に操り、日本各地にとどまらず、世界の主要都市のダンスフロアを夜な夜な沸かせている他、Mansfieldをはじめ様々な名義で楽曲制作やリミックスを手がけている。
池田:僕がやってたレギュラー仕事は、月イチじゃなく、毎週だったんですけど、そのレギュラー一本がヒットしたら割と生活出来てしまうんですよね。で、向こうの家賃って週払いだから、毎週のギャラから家賃を払って、残ったお金でレコードを買うっていう。まぁ、今もそういうシステムでやっているのかどうかは分からないですけど、ロンドンのそういうやり方が当時の自分にとっては普通だったから、帰国後に東京でDJをはじめた時システムの違いに、「これじゃ、食っていけないかも?!」って焦りましたね。
あとはすごい思ったのはラジオの影響力。ロンドンではどこ行ってもラジオが流れてて、そこではDJがチョイスして、かけたいものがかかってるし、さらには海賊ラジオがあって、その日の気分、聴きたい音楽で局を選べるし、その地域ごとにコミュニティーFMがあって、自分の住んでる街を盛り上げようとしてる。僕も(ジャー・シャカを筆頭に、ティッパ・アイリーやスマイリー・カルチャー、マキシ・プリーストを輩出した)サクソン・サウンドシステムがやってた海賊ラジオでなぜかゴスペル・タイムを担当することになった挙げ句、警察とのいたちごっこに巻き込まれて、「お前は日本人だから先に逃げろ!」みたいな。(笑)。
— はははは。海賊ラジオって、どういところでやってるんですか?
池田:イースト・ロンドンの黒人が住むエリアにあるマンションの一室が多かったですね。窓から外に向かってアンテナを出して、トランスミッターとターンテーブル2台、アンプにマイクって感じの機材で、バレたら、警察が踏み込んできて、全部没収されるっていう。その繰り返しなんですけど、とにかく楽しいから、みんな懲りずにやるっていう(笑)。まぁ、国も違えば、文化も違うし、東京とロンドンは比較にならないというか、どちらがいい悪いってことではないんですけど、僕が住んでいた頃のロンドンは、そんな感じで音楽が完全に生活の一部でしたね。
— そして、8年近いロンドン生活を経て、活動の拠点は東京へ。
池田:ロンドンでは友達が働いてた映像のスタジオで、音楽ソフトではなく、アドビのPremiereっていう映像編集用のソフトでコラージュを作り始めて(笑)。帰国してからは、当時、DJにリミックスを頼むのが流行ってたから、リミックスを頼まれるようになって、最初はお金を払ってエンジニアの人と作業を始めたんですけど、そのうちにトラックが作れるようになったんですよね。当時の初期作品は今作ってるような打ち込みの要素が全くなく、全部サンプリングで作っていたんですけど、契約上の問題になるということで、打ち込みの比率が増していって。あと、当時は何も考えずポップ・ミュージックを作ることに楽しさを覚えていたというか、作りながら勉強して、しっかりしてきたのは最近の話ですよ。
— いやー、でも、2000年からスタートするオフィシャル・ミックスCD『SPIN OUT』シリーズは、総計10万枚以上のセールスの大ヒットを記録したじゃないですか?
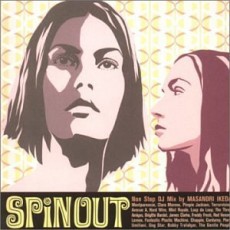
池田正典『SPIN OUT』
長らく身を置いてきたイギリスのレアグルーヴ/ジャズ・シーンの発展形である90年代後半以降のブレイクビーツ・エラに呼応。池田正典の名を世に知らしめた2000年のファースト・ミックスCD。本作含め、4作がシリーズでリリースされたほか、後続のミックスCDシリーズ『Playroom』も同じく4作がリリースされている。
池田:でも、イギリスと日本ではDJのセットも内容は変わってくるし、レアグルーヴを掘り尽くして別の音楽を掘るように変化していくなかで、「これからはそういうレコードをサンプリングした新しい音楽が面白くなるんだろうな」って思ってた時期に帰国したので、自分のなかでは過渡期にあたる時期だったんですよ。そして、帰国してプレイするようになった当時思ったのは「生の音楽をかけるとフロアから人がいなくなっちゃうんだな」ってこと(笑)。だから、より新しい方向に行こうと思ったし、なにより東京では集客力がゼロの状態からの再スタートでしたからね。そうやって東京でDJをやるなかで「ミックスCDを出さないか」っていう話が来て、それが『SPIN OUT』になるんです。
— なるほど。
池田:「BLOW UP」のコンピレーション用に使用許諾を取ったライヴラリ音源(ジェームス・クラークの「Blow Up A Go-Go」)を日本のレコード会社がシングル・カットしたいということで、その曲を中心にしつつ、「いま昔の音源をまとめても面白くないと思うんで、今のブレイクビーツを入れた方がいいんじゃないですか?」ってこちらから提案したら、「じゃ、お任せしますよ」ってことになったので、ざっくりミックスを作ったんです。それが想像を超えて売れたのは良かったんですけど、ミックスCDと実際の現場は違うものなのに、聴き手にはそのミックスのイメージが付いてしまって、自分とのズレが生まれてしまったというか。だから、自分のなかではかなり葛藤があったんですけど、それがここ何年かでようやく解消されて、現場に来てくれる人には理解してもらえるようになった手応えがありますね。
— 近年の池田さんといえば、ディスコやハウス、バレアリックを軸に、よりフリーフォームなプレイスタイルへと変化していっていますよね。

池田正典『New Balearic House』
トランスやプログレッシヴ・ハウスの回転数を落としたスクリュー・ミックスにバレアリック感覚を見出した2008年リリースのミックスCD。池田氏本人によるウィリアム・ピット「City Lights」のカヴァーを収録。
池田:『SPIN OUT』の後は『PLAYROOM』っていうミックスCDシリーズを始めるんですけど、自分は常に次の展開を求める単なる音楽ファンなので、音楽性も変化していくのは自然なことなんですよね。10代の自分は常に新しいものをディグするモッズ、モダーンズっていう概念に影響を受けたっていうのも大きいとは思うんですけど。
— たとえば、80年代のポール・ウェラーなんかにしても、モダンなものを追求する過程でヒップホップやハウス、アシッド・ジャズを広く紹介していましたしね。
池田:そうそう。「BLOW UP」のDJをやってたアンディって友達は、いまポール・ウェラー・バンドのベーシストだったりするし(笑)。ポール・ウェラーもそうだし、デヴィッド・ボウイ、ザ・キュアーなんかも作品を出すたびに音楽性が変わってて、それが常に面白かったし、子供心に憧れていた音楽体験は自分にとって大きいんですよ。
— いまの池田さんがハウスやディスコに感じている面白さというのは?

池田正典『Silent Dream 2』
『NEW BALEARIC HOUSE』で新境地を切り開いた池田氏のチルアウト・サイドが展開されている2008年のミックスCD。DJ NORI「Nomad」ほか、Flower Recordsの音源のみで構成されている。
池田:基本的に長らくDJをやっていると、プレイスタイルがどんどんロング・プレイになるというか、ディスコやハウスを延々とプレイする気持ち良さに目覚めたということもあるんですよね。あと、イーブン・キックのフォーマットに色んな音楽を放り込めるから、今やハウスといっても、キックが4つというだけで、上に乗っかっているものはものすごい幅があるじゃないですか? 2008年にリリースしたミックスCD『New Balearic House』にしても、あのミックスCDでのテンポの速いギターシンセの入ったトランスやプログレッシヴ・ハウスをピッチダウンしたスクリュー・ミックスっていうのは、自分にとってのバレアリック再解釈だったというか、ハウスにしろ、テクノにしろ、2000年以降のものはよりフリーフォームになっていったし、自分にとって面白い音楽をどんどん掘っていった結果が今のプレイスタイルなんですよ。
— そうかと思えば、今回作っていただいたDJミックスは夏仕様のジャズ・ファンク・ミックスになっていますけど、池田さんの懐の深さを実感させられる内容ですよね。

IKEDA X『Vol.01』
「池田○典氏の弟」というふれこみで降って湧いたように登場した池田正典氏の覆面リエディット・プロジェクト。アシュレー・ビードルにヘヴィ・プレイされた「PA 212516 / SC OF G.B」ほか、ガラージ・クラシックやイタロ・ディスコのエディットなど、全9曲を収録した2011年作。
池田:ありがとうございます。エレクトリック・ピアノが利いたフュージョンとかが自分の中ではまた盛り上がったりしているということもあって、今回のミックスはこういう内容になっているんです。一昔前まで、フュージョンはみんなに敬遠されていた音楽だったというか、以前レア・グルーヴ・シーンでは「年代でいうと72年くらいまでのフュージョンはファンキーでいいけど、それ以降はダメ」っていう流れがあったと思うんですけど、音楽の捉えられ方も時代と共に変わったこともあって、自分なりのジャズ・ファンク・ミックスを作ってみました。
— 作るといえば、池田さんの近年の音楽制作に関してもおうかがいしたんですが。
池田:Beatportやヴァイナル・オンリーで発表したダンス・フォーマットのEPを毎年リリースしてきて、そういうトラックがアルバムにまとまる分くらいあるんですよ。だから、「作品集として出そうか?」っていう話をFlower Recordsと進めているところです。
あと、去年、自分の弟という設定のIKEDA X名義でリエディット集をリリースしたんですけど、こちらとしては親父ギャグのつもりだったのに、みんな、本気で弟だと思ったらしくて、それが結構ショックだったんですよね(笑)。だって、「IKEDA XをDJで呼びたいんですけど、連絡先ご存じですか?」って話がありましたからね! だから、IKEDA Xは自分のことだとここで公表させていただきます(笑)。ちなみにX名義のDJは付けひげをしてプレイする設定なんですけど、鼻の下がむずがゆいのでプレイしたのは今のところ3回くらい。かける曲も普段の時とX名義では分けられないので、どうしたらいいんだろうって(笑)。
■Twitter
http://twitter.com/ikedamasanori
■Facebook
http://facebook.com/masanori.ikeda.50
■SoundCloud
http://m.soundcloud.com/masanori-ikeda
■Beatport
http://www.beatport.com/#/search?query=Masanori+Ikeda
池田正典 DJスケジュール
6月5日(火) @三軒茶屋 Orbit
6月8日(金) @青山 OATH
6月13日(水) @渋谷 BALL
6月15日(金) @渋谷 SECO
6月26日(火) @千駄ヶ谷 bonobo
6月29日(金) @渋谷 Organ Bar