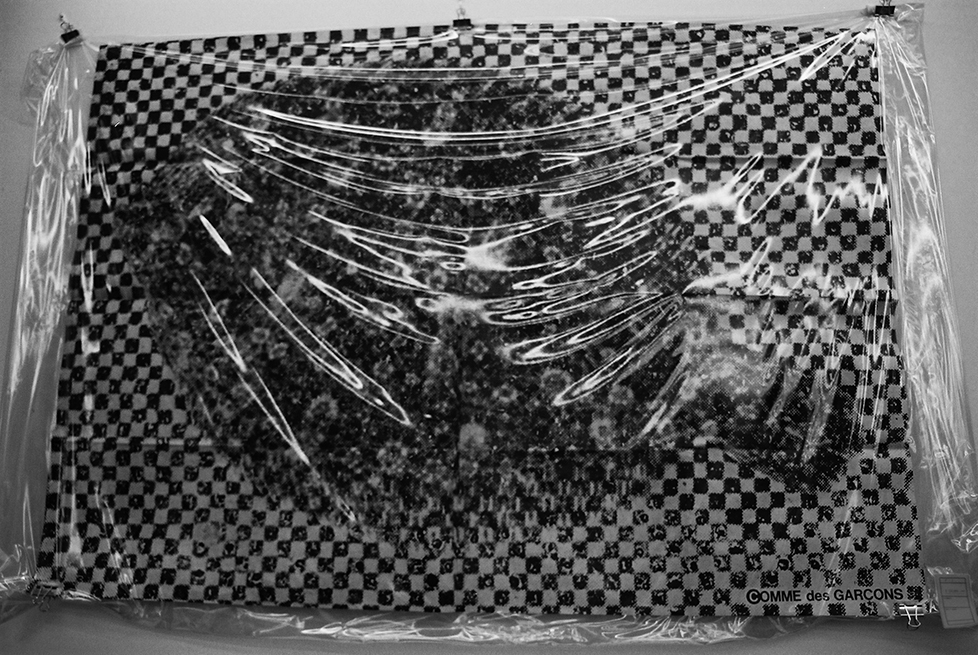Photo:ko-ta shouji | Text&Edit:Keita Miki
「色々なことが重なった結果、たまたまスタイリストになった人が本当の意味でのスタイリストなのかもしれないですよね」
— ご出身は熊本県ですよね? 家族構成はどんな感じだったんでしょうか?
島津:兄と姉がいて、僕は末っ子。兄は7つ年上なんですが、ドラムが上手くて、熊本で箱バン(特定のライブハウス専属のバンド)を長いことやってました。で、姉はピアニスト。
— 島津さんの音楽好きはご家族の影響が大きいんですね。
島津:兄はLed Zeppelinをはじめとしたハードロック、姉はCarole King(キャロル・キング)、Joni Mitchell(ジョニ・ミッチェル)といったシンガーソングライター系のレコードを集めていて、家にはレコードが沢山ありました。日本の音楽だと松任谷由実、シュガー・ベイブ、はっぴいえんどとか。僕は兄と姉、どちらの影響も受けていて、小学生の頃から色々な音楽を聴いて育ちました。
— その時代、熊本でその趣味だと、同年代の友人とは話が合わなそうですね……。
島津:もちろん、全く話は合わない(笑)。TVのチャンネルも熊本では4つくらいしか無かったような時代なんだけど、僕はおばあちゃんっ子だったから、TVも昼は『新日本紀行』、夜は歌舞伎をおばあちゃんと一緒に見るって感じで。今思えば、それはそれで良かったようにも思いますけどね。
— 子供らしい子供では無かった、と。
島津:うん、そうかもしれない。The Beatlesが好きで、写真集が入った限定のレコードボックスをお年玉を貯めて買ったりしてましたね。小学生がお年玉で買うようなものでは無いと思うけど(笑)。でも、その手のレコードが家にはたくさんあって、物珍しさからか、家に帰ると、自分は家にいないのに友達が既に何人か家にいるって状況が日常的にあって。未だに同窓会で当時の友達に会うと、「島津のおばあちゃんにはすごくお世話になった。毎日家に行くのが楽しみで仕方なかった」って言われますよ。
— レコードの情報はどこから仕入れていたんですか?
島津:主にレコード屋さんかな。手書きの入荷情報が店の壁に沢山貼ってあるような時代で。中学生になってからは雑誌も読むようになりましたね。西新宿のレコード屋のブート盤を雑誌の通販ページを見て購入したり、レコードを買うために福岡に行ったり。そういうことが、自分にとってはすごく楽しかったんです。
— 中学生にして、既に立派な音楽オタクですね。
島津:その通り(笑)。本気でミュージシャンになろうと思っていた時期もありますしね。中学生からはバンドをはじめて、YAMAHAのポプコン(ポピュラーソングコンテスト)の一部門で優勝したりもしたんです。中学3年生くらいからかな、プロモーターのような会社でローディとしてアルバイトを始めて。アルバイトといってもお金はもらえないんだけど、手伝いをする代わりに、自分達のバンドがライブをする時は機材を無料で貸してくれるんですよ。アルバイトの一環として、矢沢永吉さんのライブを見ることも出来たし、最高のアルバイトでしたね。高校生になってからは、他にもアルバイトを2つ掛け持ちしていて、1つはバーテンダー。そのお店は今で言う手品バーみたいな感じで、マスターに「お前も手品をやれ」って言われて、一時期は学校でも常にトランプを持って、マジックの練習をしてた(笑)。あとは、その頃、世間でカラオケが流行り始めたから、熊本の楽器屋さんに頼んで、お店にスピーカーとか機材をセッティングしてもらったりもしてね。ここで活きるんですよ、ローディとしてアルバイトした経験が(笑)。で、手品バーでのバーテンダーのアルバイトが終わったら、24時くらいから、サイケデリックなライティングで、時々チークタイムがあるような少し大人なバーでアルバイト。そこは同級生の親父さんが経営していたお店だったんだけど、いつもアルバイトに入るとすぐにおにぎりを作るんです。お客さん1人につき、おにぎり2つ。当時の風営法では、24時以降は飲食店じゃないと営業が出来なかったんで、要はその対策なんですよね。ひたすら朝の4時ぐらいまでおにぎりを握って(笑)、カクテルを作っていました。まぁ、そもそも10代の高校生をバーで働かせていることの方が問題なんですが(爆笑)、その辺りは時代ですよね。
— 学園生活に大いに影響が出そうなタイムスケジュールですね(笑)。
島津:そのまま寝ずにバスで学校に行くんだけど、とにかく眠くて。けど、手品の練習もしなきゃいけないから、片手にはずっとトランプを握っててさ(笑)。まぁ、はちゃめちゃな生活だったけど、お陰さまで多感な10代を楽しむことが出来ました。
— 稼いだお金は何に使っていたんですか?
島津:その時に稼いだお金で、ずっと行きたいと思っていたアメリカに行きました。初めて行ったのが1974年かな。当時、熊本にとてもお世話になっていた古着屋があって、そこのオーナーの買い付けにあわせて、何人かで付いていって。1ドルが360円とかの時代で、すごく高かったけど、今でも鮮明に覚えていますね。でも、結局学校に真面目に行くのは途中で辞めちゃって。バンドの練習もしないといけないし、アルバイトが忙しかったから。
— 拠点は、その段階ではまだ熊本ですよね?
島津:東京にはちょくちょく通ってましたけどね。アメ横にCONVERSE(コンバース)のスニーカーや古着を買いにいったり、沖縄に軍の放出品を買いにいったり。色々な場所に出没してました。熊本のスポーツ洋品店のセールに行ったらCONVERSEの『JACK PURCELL』が一杯並んでて、熊本の人たちは『JACK PURCELL』なんて知らないからさ、それを全部買って、東京に持っていって売るの。熊本の学校にアイビー好きの先生がいて、その先生にCONVERSEを教えてあげて、売ったりしてたね(笑)。
— 今で言うバイヤーみたいな動きを個人でやっていたんですね。
島津:実際にアメリカに足を運んだことで、アイビー少年だった僕も、Levi’s®(リーバイス®︎)のオレンジラベルにボウリングシャツ、靴はKeds(ケッズ)のスウェードのスニーカーって感じに見た目が大きく変化して。アメリカに行ってから分かったんだけど、結局は僕らが熱中していた”アイビー”ってVAN(ヴァン)の戦略でさ。実際のアメリカにはそんなもの着ている人は誰もいなくて、時代はヒッピー最終期。完全に騙されたと思いましたね。まぁ、今で言うブランディングみたいなものなのかな?
— アメリカにはどのくらいの期間、滞在したんですか?
島津:3週間くらいかな。初めて行ったのは西海岸で、東海岸はその翌年に。2回目からは1人でアメリカに行くようになって、まぁ、それなりに危ない目にも会いましたけど、現地では僕の見た目が小学生にしか見えないから(笑)、助かったこともありました。でも、そういうことも含めて楽しくて仕方なかったですよ。
— 日本で色々な方法でお金を稼いで、その資金でアメリカに渡航するって生活を繰り返していたんですね。
島津:そうですね、粛々と。バンドも続けていたんだけど、ライブをやる度に赤字で、お金にはならなかったですね。
— その頃はまだ、将来的には音楽で生活したいと思っていたってことですよね?
島津:ぼんやりと。でも、兄貴が食えていないのを間近で見ていたし、ローディのアルバイトで、Eric Clapton(エリック・クラプトン)、Jeff Beck(ジェフ・ベック)、Aerosmith、KISSとか、「これは敵わないな」って思うようなライブをいくつも会場で実際に見ましたからね。そういう意味では、どこかで諦めもついていたのかもしれません。そのうち、一口に音楽関係といってもアートディレクションとか、衣装とか、色々な仕事があることを知って、そういうことに携わりたいなと思うようになりました。だから、卒業後の進路としては行くなら服飾の専門学校だったんだけど、お金もないし、高校を卒業したその日に夜行列車で26時間かけて、6,000円ぐらいの片道切符で東京に出てきたんです。
— 東京に出てきてからの家や仕事はどうするつもりだったんですか?
島津:すぐにHOLLYWOOD RANCH MARKETで働かせてもらおうと思ったけど、とりあえずは渋谷のバーで働いて。家については、最初は知り合いの人のところに少しお世話になって、その後、不動産屋で物件を探すんですけど、田舎者の勘なのか、「これからは原宿だ! 絶対に原宿に住もう!」って思っていたんですよね。ようやく見つけたのが四畳半、日当たり0、砂壁、家賃が月28,000円。で、その原宿の物件に住むことに決めたんです。
— まさしく”上京物語”ですね。そこから、どのようにスタイリストへの道を歩んでいくのでしょう?
島津:東京に出てきてからパンクの洗礼を受けて、まずはロンドンに行ってみようと思ったんです。そのお金を貯めるためにアルバイトを探すんだけど、東京に出てきたばかりの田舎者を雇ってくれる職場なんて水商売しかなくて、結構大変でした。
— けれど、今度はそこで熊本でのバーテンダーの経験が活きる、と。
島津:そうそう(笑)。もう店長とかすごい怖い人で、「俺は刑務所あがりだからよ」ってのが口癖だったし、朝礼の掛け声とかもすごかったんですよ、体育会系な感じで。でも、それも今の自分の糧にはなっているのかなと思いますね。
— パンクの洗礼ならぬ東京の洗礼(笑)。
島津:そのうちに原宿に住みながら、あるアパレル会社で、僕の人生において最初で最後のサラリーマンをやるようになって。それで、そこで働きながら、当時、キャットストリート沿いに”ちはる荘”ってアパートがあったんだけど、縁もあって「そこの管理人をやらないか」って誘われて、当然、管理人はタダで住めるので2つ返事で「やります!」って答えて、アパートの管理人をやりながらのサラリーマン生活(笑)。家賃が無いので、お金が自然と貯まるんですよね。夜は毎日ツバキハウスに遊びにいって、本当に『スローなブギにしてくれ』のような生活でした。
— ものすごく情報量が多いですが(笑)、ロンドンに行くためのお金も貯まるし、順調と言えば順調な東京ライフですね。
島津:21歳の時、ようやくお金が貯まったからサラリーマンを辞めたんだけど、その後も色々とアルバイトはやりましたね。東邦生命ビルの中華料理屋、東急百貨店の蛍光灯拭き、あとはバキュームカーの掃除とか(笑)。余談なんですが、そんなこんなで、フリーター生活をしていた時に、当時、チェッカーズをプロモートしていた会社の人と知り合って。その人から、まだ売り出し中だった山下達郎さんのスタッフブルゾンと物販用のTシャツをデザインする仕事をもらったのが、東京に出てきて初めての洋服関連の仕事でした。そして、いよいよロンドンに行くことになるんだけど、ロンドンに行く前にまずは陸続きで旅行がしたいなと思って、パリに入って。ロンドンには行きたくなったら行けば良いやって感じで考えていました。
— あれだけロンドンを目指してアルバイトを頑張ったのに(笑)。
島津:フランス語も全然分からなかったんですが、Yohji Yamamotoで働いていた同郷の先輩がパリにいまして。パリでは色々とその方にお世話になったんですが、何故だかその内にファッションショーの手伝いもすることになり……。まぁ、最初は雑用係みたいなもんでしたけどね。その時代にパリで見たYohji Yamamoto、COMME des GARÇONS、Worlds End(ワールズエンド)のショーは、今でも強く印象に残っています。間近でショーを見て、「パリで日本人がこんなことを出来るんだ」って感動したんですよね。もしもパリを経由せず、そのままロンドンに行っていたら、僕はスタイリストではなく、セレクトショップのオーナーになっていたんじゃないかと今でも思いますよ。自分がスタイリストを志したのは、間違いなく、この時代のパリコレがきっかけになっています。
— しばらくはパリに定住を?
島津:そうですね、例えば、パリからドイツに旅行しに行って、戻ってきたらまたパリでアルバイトをしてお金を貯めて、お金が貯まると「じゃあ次はスペインに行ってみるか」ってな感じで、2年ほど放浪生活を続けていました。
— そういったヨーロッパでの様々な経験が、現在の島津さんのベースになっているんですね。
島津:パリは当時からモードの街で、世界のファッションの中心だったので、そこで立体的なイメージをエディットするという経験が曲がりなりにも出来たのは、自分の中でも大きいですね。海外のスタイリストってロケバスの手配からキャスティング、時には編集まで、全部自分でやるんですよ。だから、僕はずっとスタイリストってそういう仕事だと思っていたし、”スタイリング + ディレクション”って仕事を日本でやり始めたのは僕が最初だと思います。本来はリアリゼーションとも言いますが、パリには服飾の美術館があって入場料もすごく安かったし、映画館も安かったから、暇さえあれば足を運んでいて、ファッションやカルチャーの大枠についてはパリで学びました。あとは、その頃から自分で洋服のバイイングも始めて、僕がセレクトした古着を日本に送ったりもしてましたね。もちろん、ロンドンにも行ったんですが、拠点は結局のところ、パリになって。日本に戻ってきたのは、1985年くらいですかね。
— 日本に戻ってきてからは、すぐにスタイリストとして活動を始めたのでしょうか?
島津:いや、原宿のカレー屋・GHEEでアルバイトをしながら、懲りずにまたバンドをやっていたんですけど、如何せんバンドはお金にならないので、バンドを辞める決意をして。その時に初めてファッションか、音楽か、どっちかに覚悟を決めないとなって思ったんですよね。結果、音楽は諦めることにしたので、パリに来た際に僕がアテンドしていた売れっ子のスタイリストの人や、マガジンハウスの編集部の人に「スタイリストをやりたいから、何か手伝えることがあれば教えてください」って相談したんです。そしたら「あんたはもうパリでスタイリストみたいなことをやってるんだから、名刺だけ作れば良いじゃん」って言われて、「あぁ、そうか」と。
一同笑
島津:そこからはすぐに『anan』のページを担当し始めて、自分で原稿も書いて。そのうちに当時の『anan』の編集長が『POPEYE』に移るっていうから、付いていって、山本康一郎くんと一緒に『POPEYE』のメインスタイリストをやるようになったんです。原稿も書かせてくれたし、ディレクションも全部任せてくれたから、Q数からタイトルまで、全部ADに指示を出して、好きにやらせてもらって。すごく勉強になりましたね。でも、ちょうど日本で渋カジが流行り始めた頃から、やっぱり海外のカメラマンと仕事がしたいなって想いが強くなってきて、また拠点をパリに移しました。それからは向こうでもBjörkの撮影に立ち会ったり、Jean-Baptiste Mondino(ジャン・バプティスト・モンディーノ)やJavier Vallhonrat(ハヴィエル・ヴァロンラット)やMax Vadukul(マックス・バドゥカル)といった当時の売れっ子カメラマンと撮影をしたり、Martin Margielaのファーストコレクションのショーも手伝ったり、ようやくやりたいことが出来るようになってきて。それが1994年くらいですかね。95年にはまた日本に帰って来たんだけど、東京に帰ってきてからもしばらくはパリにかぶれてました(笑)。
— 日本に再度戻ってきたのはどうしてですか?
島津:パリにも『Purple』が出来て、東京は東京で良いんじゃないかなと思うようになったことが大きな理由ですね。ヨーロッパに住んでいると、意外と小津安二郎や溝口健二の映画を目にする機会が多いんですが、自分が日本の文化的な歴史を知らなすぎることに気付いたんです。ヨーロッパの人のほうが自分よりも小津安二郎や三島由紀夫のことを良く知っているのが、情けなくて。そこからは日本のことを色々と勉強しましたね。それこそ古地図を買って、日本の地理から勉強したくらい。
— 古地図はちょっとやり過ぎですね(笑)。スタイリストは特に資格も要らないし、カメラマンと比較してもアウトプットが一般の人からは見えづらい職業だと思うのですが、島津さんはスタイリストという職業についてどのように考えていますか?
島津:技術論じゃなくて感性ですからね。以前に、専門学生向けにスタイリストの授業をしたことがあるんだけど、4時間の授業が計8回あったんですよ。でも正直、1回で全部終わりますからね。
一同笑
島津:真面目な話、スタイリストとしてある程度成功している人って、「スタイリストになろう」と思ってスタイリストになった人じゃないんですよ。皆、人生経験が豊富で、物事を俯瞰で眺めることが出来るじゃないですか? だから、色々なことが重なった結果、たまたまスタイリストになった人が本当の意味でのスタイリストなのかもしれないですよね。もちろん、スタイリストにも色々なタイプの方がいると思いますが、やっぱり売れている人はキャラが濃いです。ただ、スタイリストに限らず、何の仕事でもそうだけど、ちょっとした社会性は必要ですよ。「スタイリストになりたい」って人に僕がアドバイス出来るのは、そういうこと。字が汚いのも、漢字が書けないのも、箸の持ち方が汚いのもダメですよ(笑)。
— 至極全うな意見かと思います。
島津:どうしても技術論だけではカバーできないことがスタイリストの仕事には多いから。今後は今よりも更に、洋服を貸りてくるだけじゃなく、自分で表現できるスタイリストが伸びる時代が来るような気がしています。感性さえキープ出来ていれば、どんな仕事でもやり遂げることが出来ますから。その中で、他の人が思い付かないようなアイデアを持っていることが一番大切なんじゃないでしょうか。