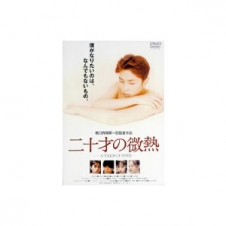前代未聞の会員制オンライン映画館『theatre tokyo』のコンセプトに共感したMasteredが、その発起人の1人である映像作家、柿本ケンサクと共に”いくつになっても輝き続けるアウトロー達の生き方の軌跡”を描いていく連載企画『シアター芸術概論綱要』。
第3回目に登場してくれるのは、1993年『二十才の微熱』にて監督デビューを果たし、以後『渚のシンドバッド』、『ハッシュ!』、『ぐるりのこと。』と独自の世界観を持った名作を生み出し続けている映画監督、橋口亮輔だ。8月31日(土)よりテアトル新宿にて公開される同人物の最新作『ゼンタイ』の発表に際して行われた今回のインタビューは、若くして自身がゲイであることを公表し、鬱病とも戦ってきた同氏による壮絶な半生と、映画業界を騒然とさせる”ある告発”を孕んだ衝撃的な内容に。この連載で初めてその存在を知るMastered読者も、どうか彼の切実かつ誠実な言葉に耳を傾けてみて欲しい。
Interview:Kensaku Kakimoto
Text&Edit:Keita Miki
実は『ハッシュ!』の根本は、浜崎あゆみという1人の”女優”なんです。
柿本— 橋口亮輔とはどういう人間ですか? 実際、世間一般的にはテーマや人間関係も含めてある一貫している部分があって、こだわりのある作品をつくり続けている映画監督というイメージです。ご自身としてはどうお考えでしょうか?こだわり続ける理由。世間の大きな流れとは違う思想や信念はありますか?
橋口:信念はここ数年で無くなってしまいましたね。例えば、一度引き受けた仕事はキャンセルしないとか。僕は”中途半端なプロ”っていうのが一番嫌いだから、そういう風にはなりたくないとかっていう信念があったんですが、これからお話しする”ある出来事”をきっかけにそういう信念も無くなってしまいました。もともと、『二十才の微熱』でデビューした時は映画監督になる気なんて全然無かったんですよ。学生時代から自主映画を作って、ハリウッドの真似事のような事をしていたんですけど、大学に入ってから初めて「映画って色々な表現の仕方があるんだな」ってことに気づいて。それからは、ずっと「自分にしか撮れない映画」っていうものを考えていました。当時は自分の性への目覚めってものも無かったし、父親からも「お前は平凡な人間だ」と言われて育ったし、小学生の時から成績もオール3。自分のことを何の取り柄もない平凡な人間だと思っていたから、果たして自分に個性のある映画なんて撮れるのか、疑問に思っていました。
柿本— 橋口監督はご自身が同性愛者ということをカミングアウトされていますが、いつごろ性の目覚めがあったのでしょうか?
橋口:あやふやでしたね。男の子が気にはなりつつも、自分に言い聞かせていた。夏目漱石が『こころ』の中で語っている、「同性愛は異性愛に向かうまでの1つの過程である」って言葉を信じて、自分を抑え込んでいました。自分は世界に1人しかいないし、何か個性があるはずだとは思いつつも、何も取り柄は無い。だから当時は、高校時代に映画制作に出会って、両親が別れて、高校で3年間ブラスバンドをやったって出来事が自分の中で最もドラマチックだったので、それを映画にしようと思って、とりあえず撮りました。でも、そうやって自分の内面と真剣に向き合った結果、男の人が好きだってことに気付いた。自分の内面なんてうっかり見るもんじゃないですね(笑)。
柿本— でも、それがやはり独特な世界感を創造して、人間という一つの大きなテーマにぶつかっている気がします。
橋口:自主制作映画だけは自分の記録として撮り続けていくんですが、プロの映画監督になろうなんてことは夢にも思わなかった。それがたまたま『ぴあ』で賞を獲って、プロの映画監督として映画を撮ることになったんですが、賞を獲ってから2年半、一向に映画制作が進みませんでした。何故かというとプロデューサーに「ホモの気持ちが分からない。何で男が男と寝るの?」と言われ続けたから。それで2年間、延々と脚本を書きなおし続けました。でも、そのお陰で「どうやったら伝わるんだろう?」ってことをものすごく考えたから、書く力は圧倒的につきましたね(笑)。
結果として、『二十才の微熱』は監督も俳優も無名だけど大ヒットして、ベルリンをはじめ、色々な映画祭にも呼ばれました。そんなこんなでなるつもりの無かった映画監督になったんですが、当時は「なんでこんな映画を作ったんだ」とか、「ゲイを売り物にするな」とか、散々言われましたね。でも、自分としてはあくまでも自主映画の延長であって、その後の『渚のシンドバッド』だって、高校生のときの自分の初恋を存在化させてあげたいなと思って作った作品だったんです。ただ、全部実話という訳では無く、発想は僕の個人的なものでも、世界で誰が観ても分かるような普遍的な表現にしていくってことは常々考えていることですけどね。
柿本— ゲイっていう出口の在り方になってるだけで、表現時代は監督が自分の内面と向き合い続け、そこから生まれた人間の普遍的な生への問いかけみたいなものですもんね。表現して作品を作り続けるということに関してはそこから順調だったんでしょうか?
橋口:充実してたんじゃないですかね。でも、自分自身の評価と、世間の評価があまりにも異なるので悩んだ時期もありました。以前に、淀川長治さんと対談させて頂いたんですが、その時「あんたはビスコンティや溝口健二と一緒で、他人のハラワタを掴んで描く人間なんだから」って言われたんですよ。「今は映画のことはどうでも良い。三島(由紀夫)読んで、歌舞伎見て、オペラを見ろ。でも、あんたは1回映画を選んだんだから最後まで映画をやりなさい」って。その対談は今でも僕の心の中にすごく残っています。「もう映画辞めようかな」って思った時には必ず先生の言葉を思い出す。その後は、歌舞伎もオペラも見たし、芝居の脚本を書いたりだとか、テレビの司会の仕事をしたりとか、今までやったことの無いことは全部やりました。それが『ハッシュ!』を撮るまでの僕の5年間。他の映画の話も頂いたけど、僕が次に撮るのは『ハッシュ!』だって決めていました。
柿本— 『ハッシュ!』は自分にしか撮れない自信があった?
橋口:ありましたね。例えストーリーを丸々真似されたとしても、1つ1つの細かい描写に関しては僕にしか撮れないと思っていました。
柿本— 『二十才の微熱』以降、制作の現場で文句を言われることは無くなった?
橋口:いやいや、全然ありましたよ。例えば、東宝とかだと大きな会社だし、”大東宝”っていうプライドもあるんでしょうね。作品を撮ってるときに高い所からの画が欲しかったんだけど、クレーンが無い。じゃあ「ロケバスの上に乗って撮りましょう」って言ったら、「そんなみっともない真似は出来ない」って言われたり(笑)。細かく言えば切りがないですけど、そういう不自由さは制作の現場では常にあります。だけど、そういう環境の中で撮った『渚のシンドバッド』は、僕自身一番好きな作品ですよ。NYでの体験もあって、初めて自分を全肯定することが出来た。あんなものづくりが出来る体験はもう2度と無いだろうなと思います。
柿本— そのNYでのエピソードが掲載されている橋口さんの著書『僕は前からここにいた』も以前に読ませてもらったんですが、この連載で僕が言っていることに近い部分が多々あるんですよね。
橋口:人間が抱えてる憎しみとか負の感情とか、そういう部分に向き合って自分を見せていくと相手は必ずボールを返してくる。昔は相手からどんなボールが返ってくるか分からない恐怖心みたいなものがあったけど、NYでの体験を通して、それが無くなりましたね。
柿本— 何が振りかかってきても、抵抗せずに受け入れるっていうある種の潔さを感じました。
橋口:そんなに格好良いものではないけどね(笑)。ゲイって言葉もまだ世の中に流通していなかった時代に地方で育ったから、誰にも言うことは出来ないし、自分は醜いんだっていう卑下もあった。そういう中で、気付けば人との距離をものすごく測る人間になっていたってだけのことです。
柿本— その開かれた状態から、『ハッシュ!』を撮ることになるわけですよね。
橋口:そうですね。今まで隠してきた自分の欲望を全部外に出して、過去への清算はついた。じゃあこれからどう生きるのかっていうのを考えたのが『ハッシュ!』でしたね。もちろん映画は好きだし、今後も撮り続けていこうと思っているけど、もしも映画以外の人生が訪れても自分が幸せだったらいいやと思って。とにかく自分が楽に、自分の中にあることを普遍的に表現しながら幸せになることを考えていました。その中の1つのアイデアが『ハッシュ!』という映画なんですが、実は『ハッシュ!』の根本は、浜崎あゆみという1人の”女優”なんです。『渚のシンドバッド』に彼女が出演した時はたしか17歳だったと思うんですが、その時に「なんて素晴らしい女優なんだろう」と思って、あゆみが主演する映画を撮りたいと思ったのが『ハッシュ!』のきっかけ。ゲイのカップルに育てられた17歳の女の子をあゆみに演じてもらって、普通の家庭で育った男の子とのラブストーリーみたいなものを作れたら良いなと考えていました。まぁ、彼女がいつの間にか歌手になってしまったのであえなく断念しましたが(笑)。
でも、その中でそもそもゲイのカップルが何故子供を育てようと思ったのか、そこを考えている内に『ハッシュ!』の形が出来上がったんです。生き方は一様では無い。自分自身、映画一筋!みたいな人生はつまらないなと思っていたし、それをなんとか形に出来ないかなということで作ったのが『ハッシュ!』でしたね。
次のページに続きます。