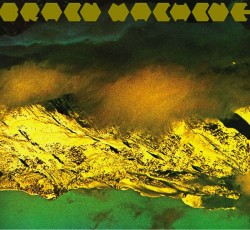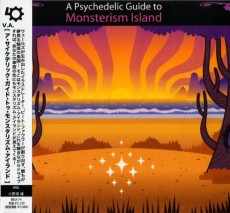昨年4月、何の前触れもなくリリースされたシングル「Astral Winds / High Tides」でダンス・ミュージック・シーンに衝撃を与えた謎のユニット、Seahawks。波のように打ち寄せる美しいノイズ、ドローンの彼方で、AORやメロウ・ポップから取られたサンプル・フレーズが浮かんでは沈む彼らの作風は瞬く間にレコード・ショップを通じて知れ渡り、後続の作品の数々はニュー・ディスコ/バレアリックやチルウェイヴ/グローファイ、シューゲイザー・シーンでクロスオーバー・ヒットを記録した。
すでに『Ocean Trippin’』、『Vision Quest One : Spaceships Over Topanga Canyon』、『Another Summer With Seahawks』という3枚の限定アルバムが驚異的なリリース・ペースで発表されているが、イギリス発のユニットということ以外、ほとんど情報が明らかにされていないこともあって、謎が謎を呼び、大きな話題となっていた。
しかし、このたび、奇跡的に彼らとの接触が成功。指定された取材場所であるウェスト・ロンドンのロフトへ出掛けると、そこにはスーパー・ファーリー・アニマルズほかのアートワーク、田名網敬一や水木しげるとのコラボレーションで知られる世界的なイラストレーター、ピート・ファウラー(Pete Fowler)。そして、1995年の設立から今年で16年目を迎えるクロスオーバーなエレクトロニック・ミュージック・レーベル、Lo Recordingsのオーナー、ジョン・タイ(Jon Tye)の姿があった。
通訳:T
写真:島崎 雄史
Seahawksのマスターは全部カセットテープだよ。フォーマットも好きだし、あの独特な鳴りが最高だよね。(ピート・ファウラー)
— これまでリリースした作品は全て限定で、あっという間にレコード・ショップから消えてしまってますし、露出もほとんどしていないこともあって、Seahawksの実体は謎めいていますよね。
ピート・ファウラー(以下ピート):そうだろうね。誰のブログだったか忘れたけど、「Seahawksって誰なの?」って書かれていたし、つい先日もDiscogsから「もう少し情報を送ってくれ」っていうメールが来たんだけど、僕たちはSeahawksをとりまく謎めいた状況が気に入っていたこともあって、返信しなかったんだ。だから、ちゃんとしたインタビューに答えるのは、これが世界初ってことになるね。
— しかも、ジョンは現在お住まいのイギリス南西部の街、コーンウォールでから4時間かけてわざわざお越し頂いて、大変光栄です。では、まずはお二人の自己紹介をお願いします。
ジョン・タイ(以下ジョン):僕は音楽を作り始めて、かなりの年数が経っているんだけど、80年代の中頃から後半にかけてFuntopia名義でGee StreetやTwo Tribeといったレーベルから、そしてMLO名義でライジング・ハイやベルギーのR&Sといったレーベルから作品をリリースしたのがキャリアの第一歩になるのかな。
いわゆるレイヴ・シーンだよね。当時、デリック・メイやトッド・テリーとも仕事をしたんだけど、エレクトロニック・ミュージック系のインディー・レーベルはまだまだ未成熟な時期で、ライセンスやお金の支払いがあまりに適当だったから、そうしたレーベルからリリースするのはやめたんだ。
それから今でこそ色んなタイプの音楽をリリースするレーベルは当たり前になっているけど、当時はロックのレーベルならロックのリリース、ダンス・ミュージックのレーベルならダンス・ミュージックのリリースといった感じで、一つのレーベルで一つのジャンルのみを扱うことが多かったから、その枠組みに収まりきらなかった僕はジャズでもロックでもハウスでも、好きな作品をリリースする場として自分のレーベル、Low Recordingsを95年に立ち上げたんだ。
— Lo Recordingsは近年、ディスコやコズミックにシフトしつつありますが、設立当初はエレクトロニック・ミュージックを基調に、エイフェックス・ツインやソニック・ユースのサーストン・ムーア、デレク・ベイリーといったレフトフィールドな作品をリリースしていましたよね。
ジョン:そうだね。設立当初はいかにいろんなミュージシャンとコラボレーションできるかというコンセプトのもと、どれくらいの音楽の幅が作れるかということを試したかったんだ。
だから、エイフェックス・ツインやデレク・ベイリー、スクエア・プッシャーやロスコー、デヴィット・トゥープ、ヨコタススムといった色んなジャンルの作品をリリースしながら、ウェスト・ロンドンのスピタルフィーリズ・マーケットにあるクラブ、Scratchで様々なアーティストのコラボレーションを意図したイベント「Extreme Possibilities Live And In The Mix」を始めたんだ。
デレク・ベイリーにスクエアプッシャー、シルヴァー・アップルズにドクター・ロッキットといったアーティストに出てもらったんだけど、みんな、面白がってくれたよ。
そして、そのイベントを2、3年くらい続けているうちに徐々に今のようなレーベルの形態になっていった感じだね。
その後、レーベル運営とDJ、ブレインマシーンほか、色んなプロジェクトでの音楽制作を並行してやってきたんだけど、そんななか出会ったのがピートだったんだ。
— 一方、ピートは、スーパー・ファーリー・アニマルズのアート・ワークを手がけたり、田名網敬一さんとのコラボレーションやエキシビジョンほかで何度も来日しているし、アート・シーンでご活躍ですよね。

Pete Fowler(ピート・ファウラー)
Sonyや雑誌GQでデザイナーとして活躍し、その後、自身のトイ・デザイン会社、Playbeastを設立。イラストレーターとしてスーパー・ファーリー・アニマルズほか、様々なアーティストのアートワークを手がけているほか、田名網敬一や水木しげるとのコラボレーションで日本のアート・シーンでも知らせる世界的アーティスト。
ピート:僕はウェールズのカーディフで、熱心な音楽ファンだった両親のもと、家でかかっていたカントリーやビーチボーイズなんかを聴いて育ったんだ。
そして、大学でファイン・アートを専攻して、ペインティングやスクラプチャー、プリンティングを学んだけど、同時にスケートにもハマって、そこからからグラフィティやコミックといった、いわゆるポップ・アートに傾倒していったんだよ。
それから、大学を卒業してからロンドンに住むようになって、イラストレーションやアートワークを手がけながら、DJも始めたんだんだけど、ロンドンに来て最初の頃は、ストックニューイントンにあるクラブで、サイケデリック・ロックやアメリカ西海岸のシンガー・ソング・ライターなど、当時のクラブでは聞けなかったような曲をプレイしてたね。
— そして、ピートは人間界とパラレルに存在するモンスターの住む不思議世界「Monsterism」をテーマに、おもちゃやキャラクター・グッズを発表していますけど、2006年に『The Sound of Monsterism Island』、2009年にその続編『Psychedelic Guide To Monsterism Island』という2枚のコンピレーション・アルバムをリリースしていますよね。
ピート:言ってみれば、その2枚は「Monsterism」のサウンドトラックだよね。『The Sound of Monsterism Island』はマーティン・デニーからシルヴァー・アップルズまで広い意味でのサイケデリック・ミュージックをコンパイルしたもの。そして、『Psychedelic Guide To Monsterism Island』はスーパー・ファーリー・アニマルズのグリフやスペシャルズのジェリー・ダマーズ、チェリーストーンズなんかに新録曲を提供してもらったんだけど、その作品にはスクオンジャックという名義で作った僕のソロ、ジョンと作ったスキットやモンスター・アット・ワーク名義のトラックも入っていて、その時の音楽制作もSeahawksの基盤になっていると思う。
— 『Psychedelic Guide To Monsterism Island』での作品は、サウンド・スケッチやコラージュ、ドローンが感覚的に表現されているという意味で確かにSeahawksと通じるところがありますね。
ピート:そうだね。Seahawksにしても同じことがいえるんだけど、僕が音楽を作るにあたっては、頭で考えるというよりは感じることを重要視しているんだ。
「いいものを作ろう」とか「この楽器を使って、こういう構成で……」といった感じではなく、自分で作った簡単な電子楽器や手近にある機材のロウファイなサウンドを自由に使った表現を楽しんでいるんだよ。
ブライアン・イーノはかつて「私はミュージシャンではない」ってことを言っていて、もちろん、彼は素晴らしい技術で楽器を扱うことが出来るミュージシャンだけど、「自分は違うんだ」と言える、そういう姿勢にはとても共感出来るね。固定観念にとらわれて、これと決めてしまわず、自由に表現することは重要だと思うな。
そして、自分のなかでは、意識して何かに似たものを作るのではなく、真っ白なもののうえに、ラフを描いて、そこから構築していくという意味では音楽も絵も一緒なんだよね。
— Seahawksの音楽からは、ノイズやドローン、アンビエントといったアブストラクト/サイケデリック・ミュージックへの傾倒がうかがえると同時に、ハイファイすぎず、丸みやあたたかみのある独特な響きに大きな特徴がありますよね。
ピート:そうだね。僕はサイケデリック・ロックやヨーロッパのエクスペリメンタル・ミュージック、クラウト・ロックが大好きだし、コルグやローランドといった機材では出せない独特なサウンドが好きなんだ。
じつはSeahawks以前に自分で作ったハンドメイドの機材を使って作ったアブストラクトなアンビエント/エクスペリメンタル/ノイズ寄りの作品を『Zombie OST』と『IIIushion Ship』っていう100本限定のカセットテープでリリースしたこともあるし、今でもそういった機材やカセットテープを使って曲作りをしてるんだよ。
ここ最近はまた見直されているみたいだけど、カセットテープの独特な鳴りにはインスピレーションを受けることが多いね。もちろん、音響的にはオープン・リール・テープがベストかもしれないけど、値段も安くないし、管理するのも大変だから、手軽なカセットテープを使うんだ。
ちなみにSeahawksのマスターは全部カセットテープだよ。フォーマットも好きだし、あの独特な鳴りが最高だよね。
— マスターがカセットテープとは驚きました。だから、鳴りが独特なんですね。そして、同時にSeahawksは70年代のAORやメロウなシンガー・ソング・ライターもの、もっと言ってしまえば、ここ数年来、一部で盛り上がってる『ヨット・ロック』(70年代の米国西海岸の音楽シーンを舞台にしたネット・ドラマ)からの影響が聴き取れます。
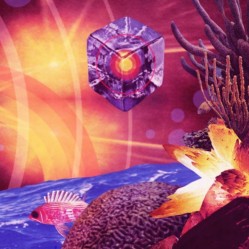
Seahawks『Ocean Trippin'』
彼らのファースト・アルバムにして、昨年リリースされた4枚のシングルをまとめたコンピレーション・アルバム。Seahawksとして初めて制作した「Omega Beach」を含む全10曲収録している。

Seahawks『Vision Quest One : Spaceships Over Topanga Canyon』
ジ・オーブの1stアルバムを彷彿とさせるA面16分、B面17分のノンストップなサウンドテクスチャーに全10曲のメロウな楽曲がフロートするディープ・チル・アウトなセカンド・アルバム。
ピート:僕は高価なプライヴェート・プレッシングのレコードよりも、リーズナブルに買えるようなもののなから、いい曲を探すのが好きで、スムースなAORを掘るのは楽しいよね。そして、ご多分に漏れず、『ヨット・ロック』の大ファンだよ(笑)。
— Seahawksのサウンドはオーシャニックな印象もありますしね。
ジョン:結局、海も宇宙も同じというか、実際に体はそこにあるけど、音楽によってどこか違う場所にトラベルできるという意味で、ぼくらのサウンドにはオーシャニックな要素が含まれていると思うよ。
ピート:と同時に、僕らの音楽にあるそうしたフィーリングはエキゾチカとしても解釈出来るんじゃないかな。マーティン・デニーにしてもそうだけど、エキゾチカは実際に存在しない、想像上でのアイランドをイメージして作られているし、作品を聴くことによって、僕らはサウンド・トラベルに出掛けることが出来るわけだからね。
ジョン:Lo Recordingsからリリースした『Milky Disco 3 – To The Stars』というコンピレーション・アルバムに参加してもらったCOS/MESにも僕らと似たようなフィーリングがあるよね。
彼らのプロダクションはアシッド・ハウスやディスコ、エキゾチカやソフト・ロックといった音楽要素を絶妙なさじ加減でミックスしていて、ジャンル分け出来ない耳新しい響きがあると思うんだ。彼らの音楽は素晴らしいよ。
— Seahawksはいまお話して頂いた様々な音楽要素が音の海に溶け込んている、そんなイメージがあります。
ピート:僕たちが最初に手がけた「Omega Beach」は、2人の間でやり取りしたドン・ヘンリー「The Boys Of Summer」のエディットがもとになっているんだけど、いま話してきたように、僕らのなかにあるサイケデリック・ロック/クラウト・ロックのアブストラクトなフィーリングやAORのスムースなメロウネス、エキゾチカのトリップ感覚が奇をてらった訳でなく、自然な流れで溶け合っていて、自分たちにとって新しいものだったんだ。そして、この作品をリリースしようと思ったことがSeahawksとしての活動につながっていった感じかな。
ジョン:でも、最初は売れるなんて全く思ってなかったし、売れなくてもいいと思ってたよ。だから、最初は200枚、300枚といった少ないプレスで始めたんだけど、リリースを重ねてくうちにイジャット・ボーイズのダンだったり、色んなDJが僕らの作品を気に入ってくれたこともあってか、徐々にシーンに知られるようになって、プレスの枚数も増えていったんだよ。
— そして、作品リリースに関しても、7インチ・シングルに7曲入りのCDが付いた最新作『Another Summer With Seahawks』やピクチャー・ディスク仕様のLP『Vision Quest One:Spaceships Over Topanga Canyon』など、リリース・フォーマットやアートワークにもかなりこだわっていますよね。
ピート:そう、僕らにとってフィジカルなフォーマットは大切な要素だよ。ダウンロードを批判する訳ではないけど、みんなが作品を手に取って、アートワークとともに楽しんでもらうために、常に作品のフォーマットには重点を置いているんだ。
そして、アートワークやフォーマットのアイディアも音と同じく、無理をして生み出されたものではなく、ただ、「好きだから」というシンプルな動機から自然な流れで生まれてきたものだし、Seahawksのアートワークはジョンと二人で作っているところも一つの特徴なんじゃないかな。
ジョン:お互い、雑誌やネットから探してきたイメージを持ち寄って、楽曲制作と同時進行、同じプロセスで進めていくんだけど、その時々で曲のイメージ合うように変えていって、最終的に楽曲が仕上がるときにアートワークも出来上がる感じだね。僕らにとって音楽とアートワークは同じくらい重要だし、分かちがたく結ばれているから、こうしたプロセスがSeahawksには合ってるみたいだ。
— 最後に今後の予定を教えてください。
ピート:『Another Summer With Seahawks』のリリースに続いて、COS/MESリミックスを収録した12インチ・シングルを出す予定だよ。
そして、まだ名前は言えないけど、今はイギリスの新人バンドのリミックスを作りつつ、Seahawksとしてはオリジナル・マテリアルのファースト・アルバムを楽しみにしていて欲しいな。
それからDJはブリックレーンにあるBIG CHILL BARでマンスリーのレジデント・パーティをやってるんだけど、今後はバンド編成でのライヴもやりたいと思ってるし、近々、日本にも行けたらいいね。
特別公開!ピート・ファウラーのワークスペース拝見
世界的なイラストレーターであるピート・ファウラーの作業スペースも合わせて特別公開!貴重な機会をお見逃しなく!
BONUS BEATS & PIECES
音だけでなく、ヴィジュアルにも飛ばされるSeahawksのTeaser映像。