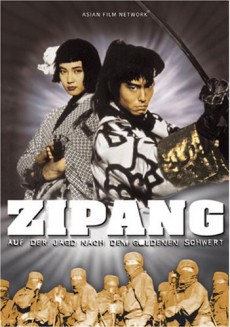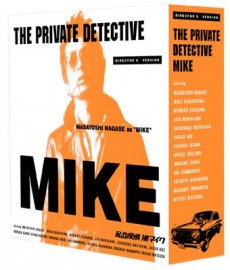前代未聞の会員制オンライン映画館『theatre tokyo』のコンセプトに共感したMasteredが、その発起人の1人である映像作家、柿本ケンサクと共に”いくつになっても輝き続けるアウトロー達の生き方の軌跡”を描いていく連載企画『シアター芸術概論綱要』。
記念すべき第1回目に登場頂くのは、『私立探偵濱マイク』シリーズをはじめ数々の名作を生み出してきた映画監督、林海象。theatre tokyoのキュレーターの1人であり、永瀬正敏、井浦新、佐野史郎らをキャストに迎えた謎の映画『彌勒 MIROKU』の公開を今夏に控えている同人物にたっぷりと話を聞いた。
Interview:Kensaku Kakimoto
Text&Edit:Keita Miki
今の状況には賭けずに、10年、20年後の未来に”全賭け”したい。今しか見てない人ってさ、絶対に「未来が良くなる」なんて思ってないわけ。だけど、俺はそこに盲点があると思う。
柿本ケンサク(以下、柿本)— 今回は記念すべき『シアター芸術概論綱要』の第1回目ということで。THEATRE TOKYOキュレーターでもある林海象監督にお越しいただきました。まずは映画監督である海象さんですが、これまで、どのような道を通って人生を歩まれてきたんですか?
林海象(以下、林):まぁ映画はね、結構長くやってきたんですよ。最初に作ったのは28年前の『夢みるように眠りたい』って映画。当時、俺は27歳でさ、東京に出てきて、もう7年以上経ってたんだけど、もうとにかくものすごく”映画監督”になりたかったわけ(笑)。
でも、映画監督なんてどうやってなればいいか分かんないじゃん。撮影所に入ってるわけじゃないし、映画学校に行ってるわけでもないしさ、無茶苦茶遠い存在なわけよ、”映画界”っていうのが。”映画監督”なんて、どうやったらなれるのか、見当も付かなかった。言うならば暗黒時代だよね。アルバイトを何個も掛け持ちしてたけど、飯も全然食えなくて。歳をとるごとに、どんどん映画が遠くなっていくんだよ。そんな時に突然さ、俺の弟が死んじゃったのよ。19歳で。病気でね。俺、本当にびっくりしちゃってさ。男なんて20歳からが面白いのに、弟の死を目の当たりにて、何も出来ずに死んじゃう人もいるんだってことが衝撃的で。当時は「俺は映画監督になるぜ!」なんて偉そうにしてたけどさ、その時に、結局俺はアルバイトも含めてあらゆるものが続かなくて、自分の人生の中で何一つやり遂げたことがないってことに気づいたんだ。「俺、何やってるんだろう」って思って。と同時に「映画監督になるには、映画を作ればいい」っていうものすごくシンプルなことにも気づいた。だから、全力をかけて、どんなことをしてでも映画を1本だけ作ろうって決めたんだ。それで生まれた映画が『夢みるように眠りたい』。
柿本— 弟さんの死がきっかけで、人生が動き始めたんですね。
林:うん。シンプルなことなんだよね。何かがが終わると、何かが始まる。そういうもんだよ、人生って。最初、まずは脚本を書いたんだ。で、映画をつくるにはプロデューサーが必要じゃん。だから、ツテを使ってプロデューサーに会いに行ったんだよ。「この本、読んでみてください!」って。で、読んではくれたはいいけど「これを映画にするには、すごくお金がかかるよ」って言われた。当時のお金で7,000万円くらいかな。けど、そんなどこの馬の骨とも分からない奴に7,000万もの大金が集まる訳ないじゃん? だから俺はお金を自分で用意しようって考えたわけ。もちろん、映画を作ったって失敗する可能性は大いにあるし、その後でどうのこうのいっても借金は残る。その借金はどんな仕事をしてでも働いて返すけど、実際に必死で働いても返せるお金は多分500万ぐらいだろうなって真剣に思ってさ(笑)。
とにかく、一番なりたくなかったのが、喫茶店とかバーとかをやってて「俺、本当は映画がやりたかったんだよ」とかって語っちゃうオヤジ。もう、あれだけにはどうしてもなりたくなくてさぁ…
一同笑
柿本— 結局やってないってことを自分で白状してるだけですもんね(笑)。
林:ごめん、ちょっと話が逸れちゃったけど、要は「これで駄目だったら、もう今後の人生で映画のことは一切口にしない」って決意をして、予算500万円で映画を撮り始めたんだ。でまぁ、色んな人が協力してくれて、どんどん映画を作る準備は出来ていくんだけどさ、今度はその500万円を貸してくれる人がいない。そりゃあ、誰も貸さないよな(笑)。
そうこうしてる内にスタッフには声をどんどんかけていったわけ。もう後は本当にお金だけ。さすがにこれはヤバいな、と思って親に頼み込んだのよ。必ず返すから、今回だけってお願いだけって。それで、なんとかお金は借りることが出来たってわけ。
柿本— なんとかお金があつまったと。でも、そこからがまた大変ですよね?そもそも、そんな大事な作品なのに、海象さんの作った作品は、モノクロで無声映画っていう攻め具合に驚きます。全く後ろをかえりみてない感じというか、崖っぷちに追いつめられても、なお、攻めるみたいな。
林:そもそも『夢みるように眠りたい』がどうして白黒無声映画なのかって言うと、予算が500万円しかないから普通のことをしたら絶対に負けると思ったの。どうせやるなら、なるべく目立つものでやろうと。あとは、まぁ、負けるだろうなとは思ってたんだけど、2%ぐらいは上手くいった場合のことも考えるじゃん。そうなった時に映画って言うのは白黒無声からスタートしているから、1本目は白黒、2本目は白黒音声入りって感じで、映画が辿ってきた歴史をなぞるように、自分の映画を歩ませるのは面白いかなと思ってさ。大変だったし、苦労もしたけど、当時はあまり大変だとも思わなかったな。夢の中みたいなもんだからさ。例えば、今はノンリニアで編集してるけどさ、昔は手で編集してたじゃん。俺はその編集のやり方が分からなくて、ハサミでフィルムを切って、1つ1つ目で見て確認して、シーン1とか名前を付けて部屋に貼ってたんだよ。「肉眼だと見にくいな~」とか言いながら(笑)。
そしたら知り合いのカメラマンが慌てて部屋に来て「何やってんだお前! 編集って言うのは編集機って機械でやるんだよ!」って怒られたりとかさ。とにかく面白かった。そんなこんなで、1年ぐらいかけて映画がようやく出来たんだけどさ、途中で事故とかもあって予算は500万円だったのに、最終的には700万円ぐらいのお金が掛かった。俺はそれを返さなきゃならないから、アルバイトを昼と夜で2つ掛け持ちして、その合間に編集をしてるんだけど、これを4ヶ月ぐらい続けてるとさ、もう何のために生きてるのか分からなくなってきちゃうんだよね、本当に。なんか、髪も白くなってきちゃうしさ…
一同笑

林海象
1986年、モノクロ・ 無声映画『夢みるように眠りたい』で映画監督デビュー。国内外でグランプリ受賞。その他『二十世紀少年読本』(1989)、『アジアン・ビート』(1991)など。永瀬正敏の人気を決定づけた『我が人生最悪の時』『遥かな時代の階段を』『罠』の『私立探偵濱マイク』シリーズを生み、探偵ブームを巻き起こした。また、映画、ネットシネマ、コミック、とメディアを超えて展開する新しいタイプの探偵シリーズ『探偵事務所5』プロジェクトを監修。2010年、『大阪ラブ&ソウル-この国で生きること』(NHKドラマ・平成22年度文化庁芸術祭参加作品)の脚本を手がけ、同作が「放送人グランプリ2011」のグランプリを受賞した。
柿本— 僕もやってました。昼、夜バイト。撮影してて、次の月の撮影に掛かる運転資金をなんとかためて、お金ができたら撮影ができるっていう。ギリギリな感じで。
林:笑。まぁまぁ、そんなこともありながら、なんとか初上映までこぎつけたわけよ。だけど、作ったはいいけどさ、次にこの映画をどうやって劇場公開したら良いか分からないじゃん。で、全然分からないからさ、映画の16フィルムを持って、東映本社に行ったんだよ。「まぁ、映画は東映かな」とか思って(笑)。
それで受付に「映画をかけて欲しくて来たんです」って話したら、その、いわゆる、苦情処理係みたいな人が出てきてさ、
一同笑
林:なんかその苦情処理係の人も妙に優しいのよ。「君、お腹空いてる?」とか言われて、喫茶店に連れて行かれてさ(笑)。
でも、「なんか映画持ってきたんでしょ?どんな映画?」とか聞かれて、俺が「白黒の」って言い出した時点で顔が曇ってるし、「無声」って言葉が出た時には完全に引いてるわけ(笑)。
まぁ、東映の話はそれで「配給っていうのは難しいからね。こういうふうに直接来られてもだめだよ」って優しく諭されて終わったんだけど、こっちとしては700万も借金があるからさ、絶対に劇場公開出来ないと困ると。そしたら、ある時、ヘラルドエースっていう大きな会社の人に映画を観てもらえる機会があってさ、どうしたものか、その人が「良い!」って言ってくれたんだよ。だから「劇場公開をしたいんです」って話をしたら、「林君、映画を公開するのにもお金がかかるって知ってる?」って言われて。もちろん金なんか一銭もないから、それを正直に話したら、その人が「1つだけ、お金をかけずに公開できる機会がある」って言う訳よ。何かと思ってよくよく聞いてみたら「今度、新宿のコマ劇で『埋もれた日本映画祭』っていうのがあって、そこならタダでかけられるよ」って(笑)。
「いや、埋もれるも何も、まだ世間に出して無いんですけど…」って話じゃん。
一同笑
林:そんな感じですったもんだしてる内に、シネセゾンの人と知り合いになってさ、当時シネセゾンでは日本映画を上映したことが無かったんだけど、そこで公開してもらえることになった。劇場が決まると今度はさ、試写をするんだよ、映画って。評論家に観てもらわないといけないからさ。それで俺のバイト代で場所を借りてさ、ありとあらゆる評論家に試写状を送って、どれだけ来るんだろうってワクワクしてたのに、フタを開けてみたら2人しかいなくて。
柿本— えっ…2人ですか(笑)?
林:いや、本当に。試写会に来た人数が2人。その後も何回かやったんだけど全然ダメでさ。人が来ないのよ、マジで。このままじゃダメだと思って、有力な評論家の人にピンポイントで見せようと思ったんだよ。それで、今は亡くなっちゃったDonald Richieさんって人に見せたら褒めてくれてさ。まぁ、Richieさんと淀川長治さんが褒めた瞬間、試写が満員になるわけよ。面白いもんだよな、中身で見てる”本物の評論家”なんて一握りしかいない。それに並行してベネチアとかニューヨークとか、外国の映画祭もバンバン決まってさ。良い感じになってきたんだけど、そうは言っても初日は怖いじゃん。今でも覚えてるんだけど、初日は5月で、シネセゾンでは『ロッキー』と同じタイミングでの上映だった。すごい緊張して、スタッフと一緒にみんなで明治神宮にお参りに行って、いざ本番となったらものすごくたくさんの人が見に来てくれて。しかも、年寄りじゃなくて、全部若い人だよ。嬉しかったなぁ~。2週間ぐらい上映してたんだけど、最初の1週間で700万円、全額返せたし。
柿本— マジですか!すごいですね。その時点で、もう勝負には勝ったわけだ。
林:マジだよ。映画業界って精算がすごく遅いんだけどさ、シネセゾンは母体が西武だから、すごく決算が早かったんだよ。最初の1週間の結果としてもらったお金が制作資金より多かったの。その後は色々なところで上映してもらえたしさ、外国で賞も獲ったし、本当に一夜にして全ての状況が変わった感じ。なんだか長くなっちゃったけど、まぁそれから20年以上、なんだかんだで映画監督をやってますよ。自分にとって最初の映画っていうのはすごく大切で、今でもこの映画に対してはすごく感謝をしてる。この作品のお陰で”映画監督”になれた訳だからね。
柿本— 『夢みるように眠りたい』はいわゆるインディーズ映画で、それに比べると、次の『ZIPANG』は予算的にかなりの大作ですけど、大作映画の監督っていうのは海象さん的にはどうでしたか?
林:おれは馬鹿だからさ、なんとなく、500万の次は5億の映画を撮ろうと思ったんだ。何故かは分からないけど「次は5億だ!」って直感的に思って。それで『ZIPANG』って作品を用意したんだけど、これがなかなか進まなくてさ。まぁ、初めて大作ってものをやってみて、ほとほと疲れちゃったね。日本映画のやり方に。ケンサクも分かると思うんだけど、なんかこう無駄が多くてさ。結局予算が何億円あっても俺のところにはもちろん来ないしさ、それを奪いに来る奴が一杯いるわけじゃん。でかい作品にくっ付こうとしてる奴が。昔も今も変わらないよね。「監督は若いからまだ分かってない」とか言われて、金があるのにも関わらず、結果、全然思い通りに出来なかった。その時はもう本当にこんなんじゃやってられないと思ってさ、映画を辞めようって思ったんだよ。映画のことを考えるだけで吐き気がするし、どんな映画を撮ろうかってイメージすると、空に重い雲がかかってくるような感じ。
でも、そうは言っても大作だからさ、自分の生活も段々変わって来るわけよ。4畳半に住んでた人間が、いつの間にか洒落たマンションに住んでて、なんか人にも持て囃されるしさ。どっか行けばお茶も出てくるし。それで、ある時思ったんだよ。「俺は何故ここに来てしまったんだ」って。それからは毎日、ちょっとずつ生活を元に戻して、3年間かかって傲慢になってきたものを1年くらいで最初の状態に戻せた。お茶も全部自分で入れるようにしたしね(笑)。
柿本— その感じは分かります。僕も良く、モノダイエットやるんですよ。自分の作業場や家にモノが増えてくると、どんどん動きづらくなってくるんですよね。大事なモノが増えれば増えるほど。手に入れるために頑張ってたのに、手に入れてしまって必要なくなったのに関わらず、それを所持しつづける事にがんばっている自分に気付くんです。本当に大事なモノなんて、生きてる瞬間はほんの少ししか無いはずなのに。知らない間にモノで太ってるんすよね。
林:そうそう。その時ぐらいからかな、段々さっき言ってた”重い雲”も晴れはじめてさ、それで初心に立ち返って作ったのが『濱マイク』シリーズ。初心に戻って、助監督だとか制作部だとか、良くある映画館のシステムは一切使わずに作ったんだ。その時に出会ったのが行定(行定勲監督)でさ、今はすっかり有名人だけど、当時は何でもない青年でしたよ。他にも2人若いのを入れて、予算6,000万の映画を全部4人でコントロールした。面白かったですよ。それで『濱マイク』を3本ぐらい撮って…みたいなところかな。そんな感じの人生ですよ。大きな映画の話は今でも来るし、やってみると楽しい部分もあるんだけど、規模が大きいほど色々な人が出てくるからさ。大体、いつも失敗するんだよね。なんでか分かんないけど、安い映画の方が上手いんだ。
一同笑
柿本— 自分の好きなものを作りたいのか、売れるモノをつくりたいのかって葛藤がもはやないような人もいるなかで、海象さんは昔から、自分の好きなモノを作り続けてきたってことですよね。実際に、予算が大きい作品でやりにくい部分はたくさんあると思うんですが、海象さんが一番良くないと思うのはどんな部分ですか?
林:助監督システムかな。大きな作品ほど、助監督ってたくさんつくんだよ。そもそも、助監督システムっていうのは、昔の撮影所が作ったシステムだから、要はそいつを監督にするためのシステムなの。撮影所ってシステム自体がまだ生きていて、みんなそこに所属していた時代の話ね。今はみんなフリーなのにさ、そのシステムだけが残ってるんだよね。助監督が全員悪いってことじゃないけど、助監督って基本的には現場の仕切りが仕事で、”物をつくる”って体勢には入ってないわけじゃん。まぁ、なんにせよ「映画とはこういうものだ」っていう、体裁とか、キメごとや言い方が全てを邪魔するよね。「制作はこういうものだ」とか「金はかかるものだ」とか。そんなに話を大きくする必要無いのにって、いつも思うよ。どんどん自分の仲間を呼んでさ。昔の映画の作り方はもう通用しないのに、1950年代、60年代のやり方以外に拠り所が無いから、その形骸だけをなぞって「映画だ!」って言うような考え方。これがいつも俺たちとぶつかるんです。大きな映画には必ずそういう人たちがくっ付いてくるし、映画の規模が大きくなるほど、制作サイドがそういう人たちを必要だと思ってる。しかも、そういう人たちって傭兵と同じで、その現場を単純に”こなして”過ぎていくから、映画に対する愛情ってありそうで全然無いんですよね。それが嫌だったな。
柿本— 初めは純粋に、文化や技術を守りたいのかもしれないけど、知らないうちに自分の立場や地位を守ることに必死になってたり。いらないですよね。
林:そういう意味では、今度公開になる『彌勒 MIROKU』って映画は、すごくピュアな状態で、ノイズが入っていない。変な映画業界の人たちを入れずに出来たんだよ。大体“映画界”が出てきちゃうと俺はダメなんで(笑)。
いっぱい宣伝費持ってきて、ポスターとかも作って来るんだけど、とんでもなくダサイわけよ。そうなるとやり取りも大変じゃん。「また監督がワガママ言ってるぜ」とか、陰口まで言われてさ。でも、俺からすれば「お前らはどうしてこれがダサイって分からないの?」、「なんでそんな必要ないこと一生懸命やってるの?誰に教わったの?」って思う。だったら『彌勒 MIROKU』のように、最初から自分で作った方が良いでしょ。みんなで作ってるから修正も早いし。要は何が言いたいかというと、共通の感覚を持った方が良いってことだよね。『彌勒 MIROKU』ではそれが出来たと思うんだ。公開の仕方も含めてね。
柿本— 何かを作るときって、毎回初めてですもんね。セオリーやルールは過去のモノでしかないのに。知らないうちに、捕われてしまう。
林:正直に言ってしまえば、もう“映画界”なんていらないんですよ。だけど、あそこにしがみつかないと生きて行けない人たちもたくさんいて、それはそれでやっていけば良いと思う。別にそれを批判するつもりも無いしね。ただ俺たちはもうそこにいる必要はないかなって。もうそんなに長生きする訳でも無いしさ。『彌勒 MIROKU』はtheatre tokyoと組んでやってるけどさ、“映画界”の人なんて1人もいないじゃん。映画館からしたら「あいつら何やってんの?」みたいなことでしょ。もちろん、失敗するかもしれないけど、こういうやり方だと、成功した時も、失敗した時も実感がすごくあるわけ。この実感が大事だと思うんだよね。映画界はさ、この実感を預けちゃうわけ、配給とか宣伝に。劇場は宣伝が動いてない、宣伝は配給が動いてない、配給は劇場が努力してない、この言い逃れの堂々巡りなんだよ。で、俺はそれをしたくないわけ。今の世の中って何でもそうなのかもしれないけどさ、実感が無いんだよ。映画を作ってる時に大事なのって“実感”なんだよ。映画は創作だし、対社会に対する融合っていうかさ、こう、社会と向き合うことでもあるわけじゃん。だから俺にとってはその実感、ダイナミズムが映画なのよ。でも大人はみんな楽しようとするじゃん。他人に預けると楽じゃん。
柿本— 実感することの方が全然たのしいのに。
林:でもね、映画界も必ず変わるとは思うんだよ。5年後はダメでも10年、20年後。それこそケンサクたちの時代だと思うけど、俺はそこに賭けたいんだよ。今の状況には賭けずに、10年、20年後の未来に”全賭け”したい。今しか見てない人ってさ、絶対に「未来が良くなる」なんて思ってないわけ。だけど、俺はそこに盲点があると思う。未来のことなんて誰にも分からないでしょ。今は負けてるけど、次は勝つかもしれない。それは雑誌とか、こういうウェブマガジンにも言えることだと思うんですよ。若い人たちって未来を作らないと生きていけないじゃん。だから逆に気が合う。すごくシャープなんですよ。逆に今まで未来を作ってきた人たちは、状況が変わらず、もうそのまま終わった方がいいと思ってるから。
一同笑
林:いやそうなんだよ、本当に。今の状況を作ってきた人や、そこに乗っかってきた人はこのまま終わりたいわけ(笑)。
だから、こういう風に若い人たちと仕事をした方が俺もピンと来るんだよね。theatre tokyoを取り巻く状況っていうのは、自分にとってとても良いものなの。『彌勒 MIROKU』って映画は、ある意味ですごくローバジェットな映画だからさ、負けても良いんだよね。負けても良いと思うと人は強いんだよ(笑)。
柿本— 海象さんはいつも、ちゃんと青春してますよね。
林:だってさ、映画って元々若い人が撮ってたんだよ。監督も役者も全部若者で、みんなで集まって映画を撮ってたのが、いつの間にか今の状況になっちゃった。絶対に映画を作るのは若い人じゃないとダメなんだよ。老練な経験ってものももちろん大事だけどさ、そんなの大したこと無い。結局撮るものは新しいものなんだからさ。そんなことより、パッションとか”身体が動く”とかそういうことのほうが大事でさ(笑)。
そういう意味ではこれは”映画を若い人に戻す”作業でもある。今は俺が撮ってるけど、俺の作品を見て、「自分たちでも出来る」とか、「あの人がやってるくらいだったら、俺にもできる」って思って欲しい。もう23くらいで監督になっちゃえば良いんだよ。そうなれば、映画は活力を取り戻すような気がするな。
柿本— 僕も飛び込みましたね、「BAR探偵」に。
林:そうそう、ケンサクとも飛び込みで始まったんだよな! そこで映画のこととか、theatre tokyoのことを聞いて、「映画に革命を起こそう!」って盛り上がった。今こういう関係に至ってるのもケンサクが飛び込んでくれたおかげだよ。まぁ、酔ってたけどさ(笑)。
柿本— 今年はこの連載でも1年間『彌勒 MIROKU』を追いかけていくつもりなので、今回で全部喋ってもらっても困るんですが、『彌勒 MIROKU』の次のステップはどんな感じですか?
林:今は劇場をちょうど決めているところです。映画館で上映するのか、生演奏バージョンをメインにするのか。映画って1,500円くらいで見られるけど、生演奏バージョンはチケットが5,000円なんだよ。映画が5,000円って高いじゃん。でもライブって考えれば普通の価格だし。だから何か違うネーミングを考えようかなと思ってるところ。
柿本— ありがとうございます。第二回、林海象インタビューも楽しみにしています。
■謎の映画”彌勒 MIROKU”
2013年夏公開予定。出演:永瀬正敏、井浦新、佐野史郎、土村芳、大西礼芳、他
稲垣足穂(1900~1977)の小説「彌勒(みろく)」を林海象が念願の映画化。
プロの映画スタッフだけでなく、京都造形芸術大学・映画学科の90人の学生たちによって創られた、林海象と学生たちがもつ純粋な光が宿った映画。
また、林海象と永瀬正敏の「私立探偵 濱マイク」コンビが17年ぶりにタッグを組んだ作品でもある。
2013年夏公開予定。
http://0369.jp