MasteredがレコメンドするDJのインタビューとエクスクルーシヴ・ミックスを紹介する『Mastered Mix Archives』。今回ご紹介するのは、2017年10月にニューヨークの優良レーベル、RVNG Intl.より発表したアルバム『UkabazUmorezU(不浮不埋)』が世界各国様々な音楽メディアの年間ベストを席巻したサウンド・アーティスト、SUGAI KEN。
幼なじみであるサイプレス上野らと結成したヒップホップ・グループでのDJ、ビートメイクからテクノ・ユニットでの活動を経て、2000年代後半以降、ソロアーティストとして、モダンな電子音楽と和の世界の融合にオリジナリティを見出した彼は、『時子音 - ToKiShiNe-』(2010年作)、『只 - Tada-』(2014年作)、『如の庭』(2016年作)という独創的な作品を次々にリリース。各地の民芸や奇祭、日本庭園や茶道、日本絵画を含む日本の伝統文化のフィールドワークで得たインスピレーションをもとに、電子音で絵を描くような絵画的な手法、茶道の見立てと現代音楽のミュージックコンクレートをつないだ工作的な手法を駆使した作品世界は海外でも評価が高まっていった。そして、2016年にアムステルダムのレーベル、Lullabies For Insomniacsから発表した『鯰上 - On The Quakefish-』を経て、2017年にリリースした『UkabazUmorezU(不浮不埋)』は、日本の現代音楽、アンビエントやニューエイジが世界的に注目されている絶好のタイミングでワールドワイドなブレイクスルーを果たした。
今回は、3月から大規模なEUツアーを控え、更なる飛躍が予想される彼の謎に満ちた音楽世界を紐解くインタビューを敢行。さらにCOLDCUT主宰のDJミックスショー”Solid Steel”やRinse FMでBEN UFOがホストを務めるHessle Audioのラジオプログラム、イギリスの人気ラジオ局、NTS Radioなど、世界の重要音楽メディアでも披露しているDJミックスの制作を依頼した。世界がその才能を発見した今、日本でも広く知られるべきSUGAI KENのオリジナリティが際立った音楽世界をお楽しみいただきたい。
Photo:Takuya Murata、Interview&Text : Yu Onoda、Edit:Keita Miki
※ミックス音源はこちら!(ストリーミングのみ)
「”市中の山居”という昔の茶人の言葉が好きなんですけど、身は街に置いているけど、気分は山の中っていう。それが一番いいなと思って作っている音楽なので」
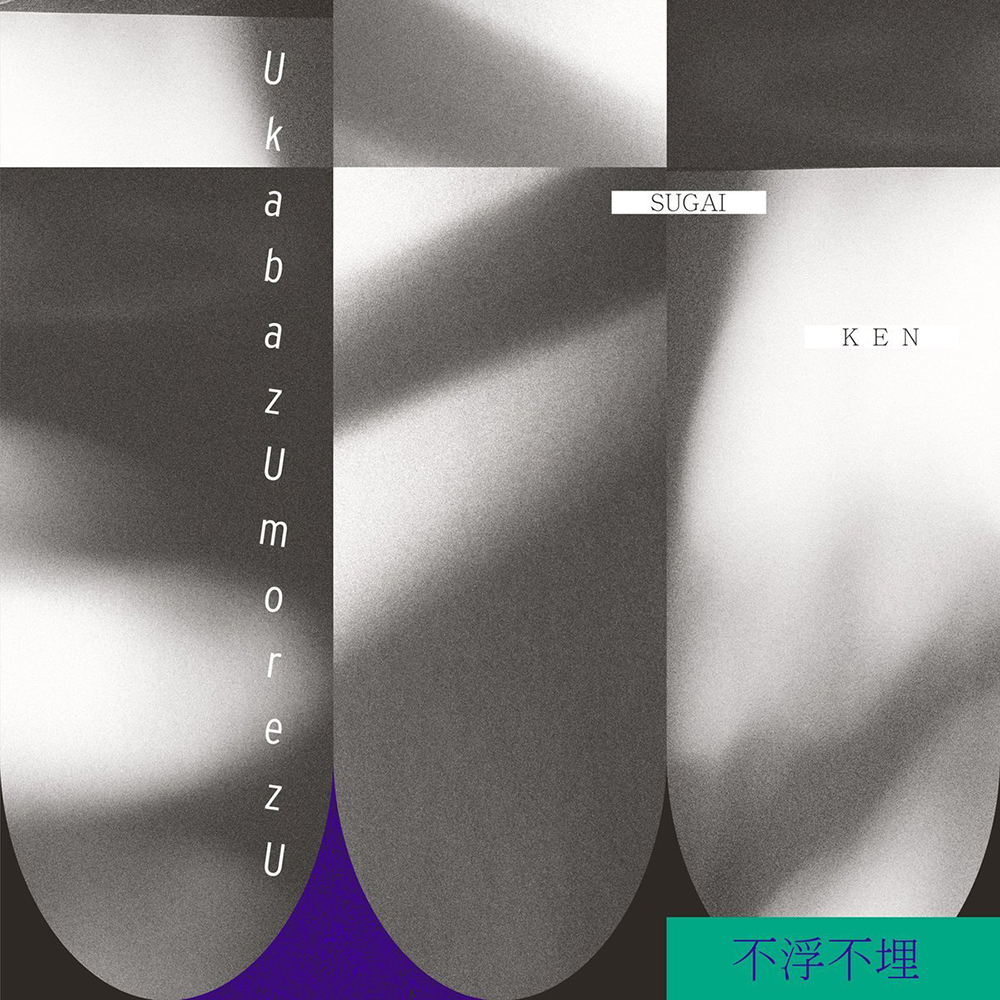
SUGAI KEN『UkabazUmorezU(不浮不埋)』
日本の伝統楽器や和のテイストを一切用いずに、日本的な情緒や情景を喚起させるモダン・エレクトロニックミュージックの傑作アルバムにして2017年リリースの最新作。アンビエントやニューエイジ、ヴェイパーウェイヴの枠には当てはまらない独創的なサウンドスケープは世界を震撼させている。
— 2017年はニューヨークのレーベル、RVNG Intl.から発表したアルバム『UkabazUmorezU(不浮不埋)』が世界各国様々な音楽メディアの年間ベストに選ばれるなど、大活躍の1年でしたね。
SUGAI KEN(以下SUGAI):ありがとうございます。ただ、年末にRVNG Intl.のショーケースツアーで(米国ポートランドのエクスペリメンタル・アンビエント・デュオ)Visible Cloaksと3公演回ってみて、彼らとのレベルの違いを痛感させられたんですよね。作品のクオリティはもちろんのこと、音楽の熱意も……ものすごい音楽マニアで、暇があれば、レコードを掘りに行ってて。彼らの音楽のインスピレーション・ソースは1970年代後半から80年代にかけての日本の現代音楽やアンビエント、環境音楽だったりするじゃないですか? そういう音楽を海外のアーティストに先越されている日本はとても残念でもあり……。
— 吉村弘さんの1982年作『MUSIC FROM NINE POSTCARDS』の再発も彼らの仕業ですもんね。
SUGAI:吉村弘さんの『PIER & LOFT』を再発したり、その辺の音楽をいち早く世界に発信してきたCHEE SHIMIZUさんのような方もいらっしゃいますけど、ホントそう思います。と同時に、彼らほどの熱意と才能を持っている人たちはいないなと肌で感じましたし、「日本人の俺らは何やってたんだろう……」とも思ったんですよね。
— しかし、もともとヒップホップのビートメイカーだったVisible Cloaksのスペンサー・ドーラン同様、SUGAIさんもルーツはヒップホップ。もっと言うと、サイプレス上野くんと幼なじみだとか。
SUGAI:そうなんです(笑)。今の彼はシーンを牽引する存在ですから、名前を出すことで他力本願だと思われたくなかったので、自分からは言わないようにしていたんですけど、あれだけカマしてる人間が近くにいることは恵まれているというか、自分にとって1つの指標になっていることは間違いないです。
— 「上ちょ」の名付け親でもあると風の噂で聞いているんですけど、彼と遊んでいるなかでヒップホップと出会ったんですか?
SUGAI:今でもその年賀状は、僕の実家の机のなかに入っているんですけど、小5か小6の時に上ちょからもらった年賀状に「ケンも早く立派なヒップホッパーになってください」って書かれていて(笑)。その頃からの彼の初志貫徹ぶりはすごいなって思いますし、中1の頃、みんなでバスケをやってる時に「雷っていうヤバい人たちがいる!」と教えてもらったのをよく覚えてますね。
— 時期的には90年代中期ですか。
SUGAI:そうですね。一番始めに行ったのは、RHYMESTER『耳ヲ貸スベキ』のリリパかな。それがクラブ初体験だったんですけど、「世の中にこんな音量がデカい場所があるんだ!」って、一瞬恐怖を覚えたくらい。実際、悪そうな人たちがいましたし、そういう怖い場所にびくびくしながら行くスリリングなところが楽しくて。そうやってヒップホップと出会って、上ちょはラップを始めたんですけど、僕は性格的に前に出ていくタイプではなかったのでDJになり、高1の頃に3MC+1DJのグループを一緒に始めて、町田の(クラブ)FLAVAでライヴやった時に緊張で手がプルプルで、レコードに針が置けないっていうDJあるある体験も味わいましたね(笑)。あと、上ちょと音楽をやっていた頃、音楽とは関係なく、自分個人では密かに掛け軸の世界に萌えていて。横山大観とか富岡鉄斎の画集を眺めてはヨダレ垂らしてる、みたいなところがあって(笑)。
— ははは。後のSUGAIさんの作品世界に通ずる渋い趣味はその頃からなんですね。
SUGAI:その後、自分の音楽に日本的な要素を取り入れるようになって、自分の嗜好について改めて掘り下げてみたんですけど、自分の母方の実家が浅草の畳屋さんなんですね。その建物は古い、薄暗い木造家屋なんですけど、幼少期にそこを訪れて、部屋の片隅の薄暗い一角だったり、入っちゃいけない部屋の存在に興味をひかれた体験がどうやら根底にありそうなんです。あと、日本的なものといえば、高校生の頃、ヒップホップのサンプリング・カルチャーにおいて、アメリカ人がそのルーツであるソウルやレアグルーヴを掘ってサンプリングしているんだったら、日本人である自分は何を掘ればいいんだろう? って考えたことがあって。でも、当時はその先には踏み込めず、その問いはぼんやりしたままでしたし、掛け軸の世界とヒップホップが繋がることもなく。その後、上ちょ達とは方向性にズレが生じて、脱退してから大学進学を機に横浜から都内に出たんですけど、去年、上ちょが出した自伝『ジャポニカヒップホップ練習帳』を読んだら、当時の彼には深い考えがあって、僕の感覚は一段階浅かったんだなという気づきもあったりしましたね(笑)。
— その後、SUGAIさんが目指した音楽というのは?
SUGAI:東海岸のヒップホップからドープなインストヒップホップ、アブストラクト。そして、大学時代の友達に影響を受けつつ、エレクトロニカ、ハウス、テクノだったり、聴く音楽の範囲を広げつつ、MPCでビートを作るようになるんですけど、当初は鍵盤が使われていることも知らなかったので、「なんで、あんなに自由なメロディが入っているんだろう?」って(笑)。そうやって最初は誰に渡すわけでもなくラップを乗せるバックトラックを作っていたんですけど、徐々に展開を付けつつ、長尺のインストに移行していって。その後、新たに知り合った4人でテクノを作るようになり、WOMBやAIRに象徴される派手できらびやかな遊び場とRAWLIFEのようなオルタナティヴな遊び場を行き来していたんですけど、その4人が散り散りになった時、派手できらびやかな遊び場は自分には無理があるし、無理せず、自分らしい音楽を作りたいと思ったんですね。そこで高校生の頃にぼんやりしたままだった”問い”と向き合うことになったんです。
— 向き合うというのは、具体的には?
SUGAI:今もそうなんですけど、例えば、ビートに琴を乗せたり、読経を乗せたりはしないんですよ。僕は庭園巡りも趣味だったりするんですけど、例えば、池があって、そこに橋が架かっていたり、石が置かれている印象的な庭園のヴィジュアルがあるとしたら、その位置を含め、音で模写するんです。だから、右の方に池をイメージした水音を配置して、左の奥に岩をイメージして、ゴツゴツした音を配置したり、そうやって風景を分解、変換して、音で肉付けする絵画的なアプローチが1つ。もう1つは、例えば、古典芸能の声や音をパーツに分解して、それを別の音で置き換える工作的なアプローチ。これは竹の置物を花入れとして用いたりする茶道の”見立て”の発想やサンプリングやミュージック・コンクレートの概念とも共通するものでもあって、実際に制作で実践した見立てを例に挙げると、雨みたいなシュワシュワした音を出すために、頭から布団を被って、そのなかで納豆をかき混ぜて、その糸引く音をマイクで録って使ったり(笑)。
— はははは! ザルの上で小豆をザザーッと流して波の音を作ったりする、映画やテレビにおける音効(音響効果)さんみたいなことですよね。
SUGAI:そうです。音効さんも大好きというか、憧れの職業ですね。僕はよく映像を消して、音だけで映画を楽しんだりもするんですけど、ハリウッド映画で活躍する一流の音効さんによるヴィジュアルを喚起させる効果音は、所謂な音響作品が吹き飛んでしまうくらいとんでもない表現世界が広がるんですよ。
— 隠れたサイケデリックサウンドであり、そうした新しい表現アプローチの追求は、新しいネタを探すためにレコードを掘るのと近いものがありますよね。
SUGAI:そうなんです。でも、面白い音は結構録り尽くされていて、水中用のマイクを取り寄せた時に調べてみたら、リチャード・ディヴァインがかなり昔にそのマイクをうごめくウジ虫の中に突っ込んで、ぐちゃぐちゃいってる音を録っていたり、1970年代にはコンタクトマイクを飲み込んで、喉を鳴らす作家のレコードがあったり。そう考えると僕がやってることはたいしたことないんですけど、絵画的なアプローチと工作的なアプローチの2つを軸にすることで、日本的な音楽要素を直接的に用いることなく、日本的なイメージが浮かび上がる曲が少しは作れるようになったかなと思います。
— 最新作『UkabazUmorezU(不浮不埋)』もそうですよね。和楽器だったり、分かりやすい日本的な要素は全く入ってないのに、何故か日本的な音楽として聞こえるのが不思議だったんですよ。
SUGAI:そういう変換作業が影響しているのかもしれないですね。あと、自分の印象的な体験としては、とあるクライアント仕事で和楽器を散りばめた曲を作ったら、「ちょっと日本的すぎる」と言われて。和楽器を全部抜いて、再度提出したら、それでも「まだ日本的すぎる」と言われたんですよね。だから、そのクライアントは自分の曲のどの部分に日本っぽさを感じたのかと考えたら、その曲には歌舞伎の冒頭でだんだん間隔を狭めて鳴らされるカンカンカンカンっていう拍子木のようなリズムパターンを用いていたんです。拍子木を使ったわけではないんですけど、それっぽい要素を入れると聴く人が勝手に日本っぽい音楽として解釈してくれるんだなって。その経験を経て、そういう音の分解の仕方をより意識するようになりましたね。
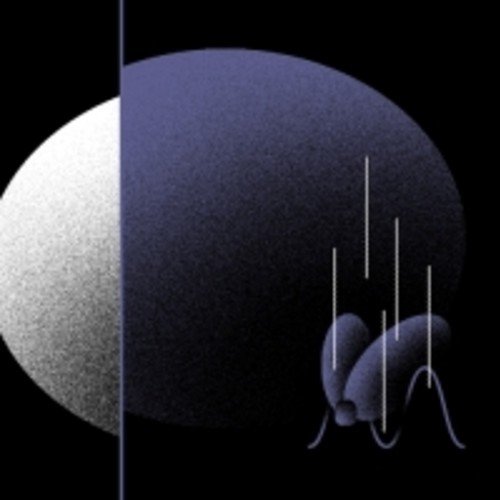
SUGAI KEN『如の夜庭』
庭で鳴く虫の音に触発され、そのサウンドスケープを描くべく、一匹一匹の虫の音を電子音で制作、配置した1時間のハードコアな音絵巻。2005年に1年の歳月をかけて制作され、2016年にEM Recordsよりリリースされた。
— そして、作品としては、2016年リリースの『如の庭』が2004、5年に制作された最初期のアルバムになると思うんですけど、あの作品では無数の虫が鳴く夜の庭を電子音で模写しているんですよね?
SUGAI:そうですね。全部で77匹いるんですけど(笑)、サイン波を加工して、虫1匹1匹の鳴き声を作って。当時はMAX MSPとか、そういう専用のソフトウェアの存在を知らなかったので、1年くらいかけて手作業でシーケンスを組んだんです。無知の成せる技というか、あまりに気の遠くなるような作業で、今だったら絶対やらないです(笑)。しかも、そうやって作ったアルバムを、その10年後にEM RECORDSの江村さんがよくぞ拾い上げてリリースして下さったなって。
— その制作過程を知ったうえで作品を聴いて、ホント驚愕しましたよ。
SUGAI:(笑)。ツールが電子音なだけで、言ってみれば、音の工作ですよね。当時はまだガンガンにテクノを作ってた時期だったんですけど、その裏でそういうアルバムを作ってて、自分にとっては明と暗みたいな(笑)。あと、そのテクノのプロジェクトはイギリスから作品リリースもしていたので、海外での活動が視野に入っていたんですけど、そこで欧米シーンの後追いをしても相手にされないだろうなという思いもあって、自分の作品を作る時は日本的な要素を上手いバランスで混ぜられないかなって思ったんです。
— 2010年のファースト作『時子音 – ToKiShiNe-』はその最初のトライアルだと。
SUGAI:『如の庭』は周りのことを考えず、自分の趣味で作った作品だったんですけど、もう少し分かりやすい要素を入れないと聴いてはもらえないだろうなと思って、『時子音 – ToKiShiNe-』は自分的にはセルアウトした作品なんですよ(笑)。
— (笑)。いやいや、今は使われていない和楽器やビートが用いられてはいるものの、全くそういう作品ではないですよ。
SUGAI:ビートやリズムの発想を盛り込んだところがセルアウトというか、自分にとっての分かりやすさだったりして。あと、和楽器に関しては、自分の根底には騙してやろうというよこしまな考えがあったりするので(笑)、本物は使ってなくて、和楽器のサンプリングとか和楽器に聞こえるようなアナログシンセを用いているんですけどね。
— (笑)。ヒップホップでいうところのハスリングに近い発想というか。
SUGAI:(笑)。まさにそう。出し抜いてやる、みたいな。

SUGAI KEN『鯰上 – On The Quakefish-』
先鋭的な作品を次々リリースし、エレクトロニックミュージックシーンで注目されているオランダ・アムステルダムのレーベル、LULLABIES FOR INSOMNIACSよりリリースされた2016年作。日本の夜の風景、その奥で広がる空想世界が具現化されている。
— 作品のモチーフに関しては?
SUGAI:(2000年リリースのコンピレーション)『響現 Kyogen』に入ってるDJ Dolbeeさんの”浅草 Asakusa”とかDJ KRUSHさんの作品にも影響を受けつつ、当初は日本的な要素を盛り込むといっても軽く考えていただけだったんですけど、叱咤激励してくれる友達から「掘り下げ方が甘い」としょっちゅう言われて、日本のコアな民芸とかお茶の世界について勉強したり、趣味を兼ねて、1人で京都のお寺を回ったり、夜行バスで全国各地のコアな郷土芸能の場に出向いて、そこで得たヴァイブス、見た空間を思い浮かべて、さらにそれを音に置き換え、ブラッシュアップしていくんですけど、そうしたフィールド・ワークが自分にとってはレコードを掘る感覚と一緒なんですよね。
— 日常では見られないコアな民芸や郷土芸能、奇祭は日本各地に沢山あるんですか?
SUGAI:星の数ほどあります。それぞれ面白いし、優劣は付けがたいんですけど、例えば、地元の人も知らなかった鳥取の麒麟獅子舞は、夜の部がエグい雰囲気が満載で、最新作に入っている”冥”という曲はその獅子の鳴き声を電子音に置き換えて盛り込んでいたりします。
— 2014年にセカンドアルバム『只 – Tada-』、2016年にアムステルダムのレーベル、Lullabies For Insomniacsから発表した『鯰上 – On The Quakefish-』、そして、最新作『UkabazUmorezU(不浮不埋)』と、作品を重ねるごとに、モチーフの置き換えや音の風景描写が抽象度を増しているという印象を受けます。
SUGAI:そうですね。だから、次に個人で出そうと考えている『時子音 – ToKiShiNe-』、『只 – Tada-』に続く3部作のラスト作は、原点に立ち返って、分かりやすくビートを盛り込んだり、クール・ジャパンをわざとぺらっぺらにリバイバルさせてみようかなと考えたりしているところです。僕の音楽は実験的ですが、その一方で弾き語りのライブが好きだったり、最近だと井出健介さんのファンだったりもしますし、メロディのある音楽も大好きなんですよね。だから、そういう感覚も忘れないように音楽に向き合っていきたいですね。
— 新作にもあちこちにシンセのメロディが散りばめられていたりもしますし、SUGAIさんの作品は実験が目的化したものではなく、絶妙なバランスのなかで音の風景が浮かび上がる作品ですもんね。
SUGAI:そうだといいんですけど、別の捉え方をすると、自分のなかで振り切った表現に恐れがあるということなのかもしれないし、無い物ねだりなのかもしれないですね(笑)。
— SUGAIさんの音楽は、アンビエントやニューエイジとも形容されたりもしていますけど、自分が作品から受けた印象として、SUGAIさんは音の風景、つまりサウンドスケープを描くアーティストという認識なんですが、ご自分ではどうお考えですか?
SUGAI:アンビエントやニューエイジという形容は、個人的にどこか違和感があるというか、実際、そうしたジャンルの王道のメソッドを使っていない曲が多いし、スピリチュアルな音楽を作っているつもりもなく、聖と俗の狭間をゆらゆらしている音楽が自分にとってすんなりくるというか、僕は”市中の山居”という昔の茶人の言葉が好きなんですけど、身は街に置いているけど、気分は山の中っていう。それが一番いいなと思って作っている音楽なので、アンビエントやニューエイジだと思って買った人が「全然違うじゃん!」って感じるんじゃないかと思っていて。まぁ、でも、ジャンル分けは聴いてくださる人の判断に負うところが大きいので、文句を言いたいわけでは全くないですし、むしろ、日本のアンビエントや環境音楽が再評価されているタイミングとたまたまシンクロしたことで、海外で注目してもらえたところもあるので運がよかったなとも思いますね。
— 海外といえば、3月末からEUツアーが始まるんですよね?
SUGAI:はい。かなりの過密スケジュールになりそうで(笑)、今は体力的にかなり不安なんですけど、GONNOさんからも「SUGAIくん、これからは体力勝負だから」ってアドバイスされたので、これから肉食って、走り込みをしないとなって(笑)。ただ、海外での反応や海外から日本を客観的に見ることで得られるものは大きそうなので、色んなものを吸収出来たらなと思ってますね。
— 最後にDJミックスについて一言いただけますか。早くも遠くなりつつありますが、2018年の一発目ということで、正月の幻影が浮かび上がるミックスというこちらの勝手な要望を汲み取っていただき、本当にありがとうございます。
SUGAI:DJでは無い立場の僕がカリソメなmixをやらせて頂くのは非常に恐縮ですが、折角お声掛け頂いた機会でもありますし面白い感じになればなぁと思いやらせて頂きました。是非楽しんで頂けると嬉しいです。

