MasteredレコメンドDJへのインタビューとエクスクルーシヴ・ミックスを紹介する「Mastered Mix Archives」。今回登場するのは、今年5月に2年半ぶりとなるサード・アルバム『Obscure Ride』をリリースした3人組バンド、ceroの高城晶平。
その最新作では、ブラックミュージックの秘史に見出したエキゾチズムと現代東京のマジックリアリズムが展開される歌詞世界を融合。音楽的に大きな進化を遂げると同時に、今年のFUJIROCK FESTIVALではホワイトステージに出演するなど、バンドとしてスケールアップを果たしたcero。そのヴォーカリスト、ソングライターである高城晶平は、近年、あちこちのパーティにDJとしても呼ばれるなど、神出鬼没な活動を行っている。今回のインタビューでは、そんな彼の音楽観を紐解くと同時に、制作を依頼したDJミックスからceroの秘密に迫ってみた。
Interview & Text : Yu Onoda | Photo & Edit : Yugo Shiokawa
※ミックス音源はこちら!(ストリーミングのみ)
『WORLD RECORD』はどちらかというとお昼の音楽なんですよね。それが作品を重ねるごとに夜に近づいていって、その次の『My Lost City』は夕方、『Obscure Ride』でようやく夜に辿りついた感じ。
— 高城くんはceroでバンド活動しながら、ここ最近はDJとして、パーティに呼ばれることも増えてますけど、DJ的な視点で聴くと、音楽の捉え方が変わりますよね。
高城:そうですね。最近の話だと、8月終わりに、Roji(高城が阿佐ヶ谷で経営しているカフェ/バー)でbeipanaさんが7インチ・シングル「7th voyage」のリリース・パーティをやることになって。そのイベントに向けて、お店でかけるBGM用に、beipanaさんから気に入ってるバレアリックなDJミックスをまとめてもらったんです。そのなかには、LEXXとかDJ HIKARUさんの音源も入っていたんですけど、例えば、80年代にアフリカ音楽に傾倒していたポール・サイモンだったり、グルーヴやリズムが立ったシンガーソングライターものの曲をミックスして、格好良く聴かせてくれるところがすごい良くて。「こういう聴き方もあるんだ!」と刺激を受けたので、父親から譲ってもらった大量のレコードを引っ張り出して、バレアリックな視点で聴けるものがあるんじゃないかとあれこれ聴いてみたんです。
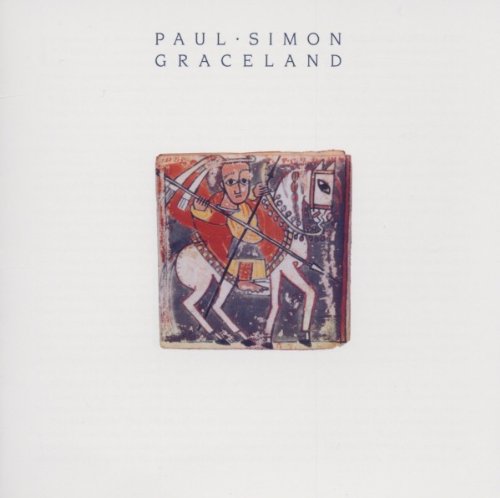
Paul Simon『Graceland』
フォークシンガー、ポール・サイモンが1985年に南アフリカで行ったセッションをもとに展開されたアフロポップの世界的ヒット作。ヴァンパイア・ウィークエンドに大きな影響を与えた作品であり、収録曲「Diamonds on the Soles of Her Shoes」はトッド・テリエのブートエディットがフロアヒットとなった。
— シンガーソングライターの曲って、歌にやメロディばかり意識が向かいがちですけど、リズムやグルーヴを意識して聴くと、曲の捉え方が変わったりしますもんね。
高城:そう、自分のなかで音楽が再編成されるような感覚があって、角度を変えて聴くと、かつては捨て曲として捉えていた曲がしっくり来たりして。DJっていうのは、聴かせて方によって、その曲に新たな価値を与える作業というか、改めて、いい仕事だよなと思ったんです。だから、こないだDJをやった時も自分なりの視点で捉え直したレコードをあれこれかけて。DJって、お客さんを踊らせることが最重要だったりするから、当初は曲の繋ぎを下手なりに頑張っていたんですけど、もっと、ゆったり聴けるDJでもいいんだよなと思い直したりもしたし、そういう視点で振り返ってみると、中学生だった僕の音楽の入口になったベン・フォールズ・ファイヴも間口の広い音楽性なんですよね。ファンクだったり、ブラックミュージックにも開かれているし、ロックだったり、ピアノ・オリエンテッドなポップスでもあったり、色んな角度から楽しめるし、そういう音楽が僕の音楽の入口で良かったなって。

Ben Folds Five『Ben Folds Five』
ギターレスのピアノ・トリオによる1995年作のオルタナティヴなパワーポップ名作。全12曲には、ソウルやファンク、クラシックやジャズなど、様々な音楽要素が溶かし込まれている。
— ceroも折衷的な音楽のエキゾチズムを求めた結果、最新アルバム『Obscure Ride』では、ブラックミュージックに辿り着いたわけですもんね。
高城:そうですね。自分が音楽でぐっとくるポイントはそういうオブスキュアなところだったりするんですよね。それこそ、前作の『My Lost City』では、80年代のZE RECORDSに象徴されるミュータント・ディスコの影響が大きかったりしたんですけど、あの辺の音楽はまさにクロスオーバーな音楽だったりするし、自分のアンテナはそういう音楽に敏感に反応しちゃうんですよね。
— 夜遊びするようになったり、DJするようになったりして、自分の音楽観にどんな変化がありました?
高城:『My Lost City』のレコーディングに参加してもらったエンジニアの得ちゃん(得能直也)に誘ってもらって、頻繁に夜遊びするようになる以前、ファースト・アルバム『WORLD RECORD』はどちらかというとお昼の音楽なんですよね。それが作品を重ねるごとに夜に近づいていって、その次の『My Lost City』は夕方、『Obscure Ride』でようやく夜に辿りついた感じ。その話で思い出したんですけど、得ちゃんをはじめ、夜遊びしている大人の人たちって、僕たちが普段ライヴをやってる19時から22時くらいの時間帯を「夕方」って言うじゃないですか?

cero『Obscure Ride』
前作『My Lost City』から2年半を経て、今年の5月にリリースされたceroの最新アルバム。先行シングル2枚で見せたブラックミュージックへの傾倒はさらに深化しつつもあくまでポップに消化された、まさにメンバーの「今の気分」が凝縮された1枚。
— 確かに言いますねー。
高城:「ああ、夕方のイベントなんだー」とか。そう言われるのがすごい悔しくて(笑)。
— 下手すると、デイ・イベントとか言われたりとか(笑)。
高城:そうそう(笑)。だから、「自分が夜だと思っていたものは夕方に過ぎなかったんだ!」と、すごいショックを受けたんですけど、夜遊びするようになって、「あ、ホントの夜はここにあったんだ」って。その体験は自分たちにとって大きかったですね。
— オールナイトの野外イベント、TAICOCLUBで、ceroは真夜中にライヴをやったりしてますよね?
高城:真夜中といっても、1時くらいですけど、夜が更けていくにしたがって、みんなの音楽の聴き方は変わっていくじゃないですか? そうなった時、真夜中に聴けるバンド音楽って限られてくるし、深夜帯を担えるバンドって、多くはないと思うんですよ。
— ceroが夜中にライヴをやった時も真夜中用のセットを考えたんですか?
高城:そうですね。「この曲を真夜中にやるのは違うだろうなー」って感じで、持ち曲を削ぎ落としていくと、必然的に決まっていくし、やっぱり、その多くは『Obscure Ride』の曲だったりするんですよ。
— 歌詞でも夜の世界が描かれていますし、サウンドプロダクションも出音のバランスや質感が変わりましたもんね。
高城:そう。低音が占める割合が多くなりましたし、スライ・ストーンやプリンス、ネオソウルなんかがそうであるように、レコーディングではドライな音の質感を常に意識してましたからね。
— ただ、ミュータント・ディスコに影響を受けた『My Lost City』からブラックミュージックに傾倒した『Obscure Ride』は音楽的な部分でかなりの飛躍がありますよね。どんなきっかけがあったんですか?
高城:バンドの流れでいえば、『My Lost City』を作ったことで、曲のストックを出し切った白紙の状態からその時に聴いていたものを踏まえて、その後のシングル「Yellow Magus」に向かっていったし、それに併せて、ベースの光永(渉)さんとドラムの厚海(義朗)さんを加えた今のラインナップになっていったんですね。でも、個人的なきっかけに関して言えば、その前段階で出会ったジェイムス・ブレイクの音楽が大きいかもしれない。フジロックで観た彼のライヴのミニマルな演奏で、よれたビートの魅力を分かりやすくプレゼンしてもらって、「ああ、なるほど!」って思ったんですね。そういう体験を経て、J・ディラやディアンジェロのビートを聴き直したら、いつの間にか違う角度から聴けるようになっていて、ビートをズラした、よれたグルーヴを自分たちのフィールドに持ってくるべく試行錯誤が始まったんです。
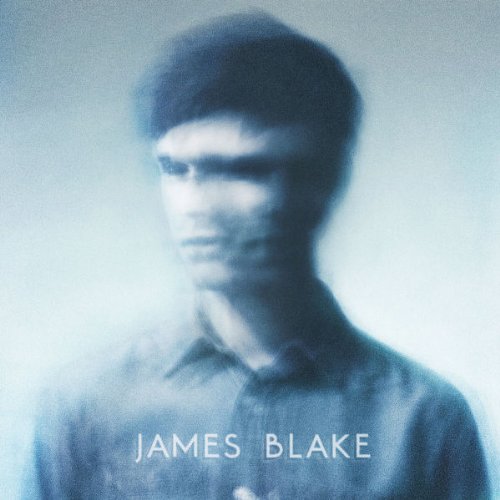
James Blake『James Blake』
超重低音を埋め込んだプロダクションにディアンジェロのオフビート感覚やJ・ディラのサンプル・チョップ手法を応用。2011年の音楽シーンに衝撃を与えたポストダブステップ界のシンガーソングライターによるデビューアルバム。
— ceroの3人も駆けつけたZEPP TOKYOのディアンジェロも、ライヴ前にJ・ディラがかかってましたもんね。
高城:延々と2周してましたよね(笑)。あと、『Obscure Ride』が誕生した背景で、影響が大きかったのは小沢健二さんの『Eclectic』ですよね。あのアルバムが出た2002年当時、僕は高校1年生だったんですけど、「今夜はブギーバック/あの大きな心」以外、よく分からなかったというか、咀嚼しきれなかったんですね。でも、夜遊びしたり、ジェイムス・ブレイクを通過した耳で改めて聴いた時に、「あのアルバムはディアンジェロ以降のブラックミュージックに即レスポンスして生まれた作品だったんだ!」と思ったし、あのアルバムが自分たちにはいい参考書になったんです。
— ちなみにディアンジェロのライヴを観た感想はいかがでした?
高城:ギター3本でがんがんに攻めるギターファンクだったことが強く印象に残ってますね。あれはジミヘンだったり、プリンスの系譜のギターサウンドだなと思ったんですけど、ああいうブラックロック感は白人のロックと何かが決定的に違うし、自分が求めるクロスオーバー感覚があるなと思いましたね。それは自分があのライヴで求めていたディアンジェロの音楽とは多少違っていたですけど(笑)、発見はたくさんあったし、すごい新鮮でしたね。
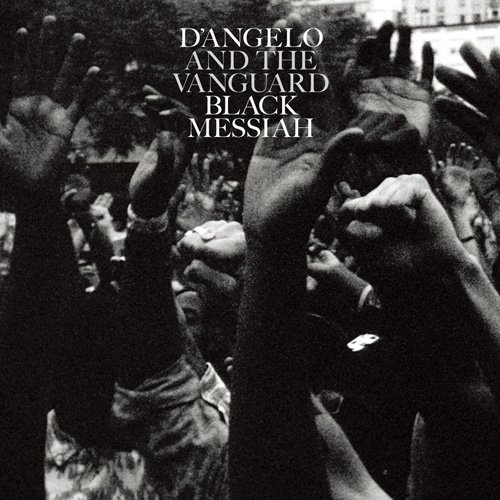
D’angelo And The Vangard『Black Messiah』
ヒップホップ、R&B世代の濃密なアフロセントリック・サウンドを確立。J・ディラとともにビートミュージックに革命を起こした
前作『Voodoo』から14年ぶりにリリースされたサード・アルバム。自らギターを手に取り、ファンクやブラックロックを軸にいびつなクロスオーバーが押し進めた作品世界は先の来日公演では怒濤のファンク・サウンドへと変換され、観る者に大きな衝撃を与えた。
— 古くはバッド・ブレインズしかり、リヴィング・カラーしかり、アイス・Tのボディ・カウントやモス・デフのブラック・ジャック・ジョンソンだったり、ブラックロック・バンドの音は白人のロックバンドと明らかに違いがあるんですよね。
高城:白人が抱えている黒人コンプレックスと真逆なコンプレックスを黒人も抱えていて、それがいびつな形に表れているのかもしれないな、と。そういういびつさが僕にとっては愛おしく感じられたりするんですけどね。
— もともと、ロックンロールはリズム&ブルースの一部だったはずなのにね。ステレオラブのレティシアが参加したコモンの『Electric Circus』しかり、確かにブラックロックのいびつさは脈々と流れていますよね。
高城:自分の音楽遍歴を振り返ると、そういうクロスオーバー感覚が一貫して好きだし、ディアンジェロのライヴにも近いものを感じましたね。あと、あのライヴでドラムを叩いていたクリス・デイヴが参加しているロバート・グラスパーのライヴなんかも、セットリストを決めずに演奏していて、その時々のライヴのムードで自然と次の曲に繋がっていくらしく、彼らのライヴを初めて観た時、曲と曲のつなぎはBPMが一定ではなかったんですけど、3連のリズムを4で捉えて、次の曲に移行していく演奏がハウスだったり、DJ的なものとしても楽しめたんですね。ceroのライヴでも曲を繋いで演奏するんですけど、ロック的にがんがん畳みかけるんじゃなく、流れのなかで曲の良さを増幅させるために曲と曲をつなごうと意識していてますね。
— ダンスミュージックやブラックミュージックをはじめ、その時々で吸収したものがceroの音楽に変換されているわけですね。
高城:そうですね。作品ごとに音楽性が変化していくと同時に、そういう雑食的なテイストが一貫していれば、自分たちの音楽の説得力も増していくんじゃないかなって。細野さんの音楽がまさにそうじゃないですか。その時期ごとに音楽性は変わっているんだけど、その変遷を追っていくと、そこには一貫性があるわけで、自分たちの音楽を後から振り返った時にもそう感じられたらいいな、と。
— では、最後に、制作をお願いしたDJミックスについて一言お願いします。
高城:インタビューの冒頭で話したbeipanaさんのミックスを聴いて、自分なりにそういう選曲をやってみたいなと集めてみました。中心にAlfred Beach Sandalの新譜から「Fugue State (feat.5lack)」を入れたんですが、その感じが、どこかダークなバレアリックな感じになっていると思います。楽しんで聴いてもらえたらうれしいです。