Vol.62 Campanella『PEASTA』リリース記念特別編 feat. Ramza & Free Babyronia – 人気DJのMIX音源を毎月配信!『Mastered Mix Archives』
by and
MasteredレコメンドDJへのインタビューとエクスクルーシヴ・ミックスを紹介する「Mastered Mix Archives」。今回は、9月7日にリリースされる2016年屈指の名作アルバム『PEASTA』誕生を記念して、その作品の主であるラッパーのCampanellaとビートメイカーのRamzaとFree Babyroniaをフィーチャーした特別編をお送りする。
愛知、岐阜、三重の東海三県の才能が集結したラップ・ムーヴメント、NEO TOKAI DOPENESS。その起点であるATOSONE率いるレーベル、RC SLUM RECORDINGSと不定期開催のパーティ『METHOD MOTEL』。その一員として、マイクを握ることもあるCampanellaが前作『VIVID』から2年ぶりに発表する新作『PEASTA』は、彼とRamza、Free Babyroniaの地元である名古屋のベッドタウン、小牧市の桃花台ニュータウンから突然変異的に誕生したレフトフィールドなヒップホップ・アルバムであり、個を尊重した真のコミュニティミュージックでもある。
客演は親交の厚いラッパー、C.O.S.A.とNERO IMAIをフィーチャーした1曲のみという本作で、RamzaとFree Babyroniaが紡ぎ出すビートは、メロウネスとスリルを内包しながら、エレクトロニカやノイズ、インダストリアル、ベースミュージックと共振。クラブのサウンドシステムから箱全体を震わせるほどの低音を放つ弩級のグルーヴに乗せ、Campanellaが何の変哲もない日常をリアルに、エモーショナルにラップすることで、そこにはドラマチックな瞬間が生まれる。その躍動感が聴く者を深く魅力するアルバム『PEASTA』の核心に迫るべく、CampanellaとRamza、Free Babyroniaに長編インタビューを敢行するとともに、RamzaにDJミックスの制作を依頼した。彼らの言葉と音を頼りに、最高のアルバムをより深く楽しんでいただけたら幸いだ。
Interview & Text : Yu Onoda | Photo & Edit : Yugo Shiokawa
※ミックス音源はこちら!(ストリーミングのみ)
このアルバムこそが真のコミュニティミュージックだと思ってます。(Campanella)
— Campanellaのキャリアは、ヒップホップグループ、L.D.K.の活動が最初だとか?
Campanella:そうです。結成は16、17くらい。最初はRamzaとの2MCだったんですよ。当時、Free Babyroniaは別のやつと組んでたんですけど、そのグループを辞めて、L.D.K.に加わって、3MCになったんです。
— RamzaとFree Babyroniaはラッパーだったんですね。他のメンバー、GiovanniとMimosa Pudikaっていうのは?
Campanella:どっちもFree Babyroniaです(笑)。ラッパーの名義がGiovanni、ビートメイカーの名義がMimosa Pudikaっていう。ていうか、結構深いところまで掘り下げるインタビューですね(笑)。
— というのも、今回のアルバム『PEASTA』のメイン・プレイヤーは、Campanella、Ramza、Free Babyroniaの3人ですからね。彼らとの出会いは?
Campanella:RamzaとFree Babyroniaは、小牧の桃花台ニュータウンにある中学の同級生で、俺は隣の中学に通ってて、2人とも不良だったんですけど、中3と高1の間の春休みに周りに数少ないヒップホップ好きとして、友達に紹介してもらって、Ramzaと仲良くなったんです。Free Babyroniaとはそれ以前からちょくちょく話したりはしてたんですけど、多分、あいつもなんとなくヒップホップが好きだったのか、高1の時に俺とRamzaがラップを始めたことで、「俺もラップやりたい」って言い出して、そんな経緯もあって、RamzaからFree Babyroniaをちゃんと紹介してもらったんです。だから、2人とは10年以上の付き合いになりますね。

Campanella『PEASTA』
10代から共に育ってきた同郷の先鋭的なビートメイカーRamza、Free Babyroniaとがっちり組んだ2年ぶりのセカンド作。全11曲に凝縮された日常のドラマチックな描写とサウンドの革新性は、ヒップホップ・リスナーのみに留まらず、幅広くアピールするはず。
— 3人の地元であり、アルバムの舞台でもある小牧の桃花台ニュータウンはどういう土地なんですか?
Campanella:桃花台は、(同郷のラッパー、NERO IMAIが「はじまりはメロディ・パーク」と歌っていることでも知られる)メロディパークっていう公園が駅前にある小牧駅から結構距離があるんですけど(笑)、名古屋から車で30、40分のベッドタウン、綺麗に区画された住宅街で、よくたむろしていたのがアルバムタイトルにもなった『PEASTA』(名称は、桃の産地でもあることから“PEACH”と祭りやパーティを意味するスペイン語“FESTA”を合わせた造語)っていう商業施設なんですよ。桃花台にはこれといったカルチャーや日常のドラマもないし、カルチャーに精通した先輩もいなかったので、自分で楽しみを見つけて、誰かと共有することもなく、自分で楽しむっていうことをずっと続けてました。
Ramza:ホント、何もない、誰もいない、クラブもなければ、長くやってる駄菓子屋や米屋、布団屋だったり、そういう歴史ある商店街もない。先輩もいない、文化不毛の地ですよ。言ってみれば、内モンゴルの草原にゲルが一棟建ってるみたいな、そんな感じというか(笑)。でも、僕たちを構成する要素として、その“何もない”ところは一つのポイントですよね。
— では、その“何もない”街から『PEASTA』という先鋭的な作品がどうして生まれたんでしょうね?
Free Babyronia:桃花台にはあまり行くところもないし、何もないから、自分は音楽やアートに傾倒してたし、得たものをみんなで共有してたんです。
Campanella:そう。myspace全盛の頃はどこかに出掛けるっていうより、ネットで掘った音楽を3人で共有していた経験がデカい気がします。
Ramza:そして、自分たちで得た情報で突き進んで楽しく遊んでいくしかなかったというか、そういう経験が今を構成してると思いますね。桃花台が僕らの音楽に及ぼした影響というのは、そんな感じかな。高校生の頃から20代前半の時期は、3人で集まって、誰が一番ヤバい音を掘ってきたか、その戦いをずっと続けてきましたからね。
— アルバムのアートワークを手掛けたrisa ogawaさんも同じ小牧の出身だとか。
Campanella:ジャケットはアルバムの第一印象になるわけで、信頼出来る人に頼みたくて。COSAPANELLAのアルバムやジュークのコンピレーション『160OR80』のアートワークも手掛けているrisa ogawaと自分の友人にお願いしたんですけど、「NINE STORIES」で歌っている「内面動向外的表現」っていうのは、risa ogawaが4月にやったエキシビジョンのタイトルなんですよね。彼らは作品自体も好きだし、忘れられないような空間の演出に長けているので、その2人にアートワークを委ねました。それから(レーベルのJET CITY PEOPLEとSTUDIO NESTを主宰する)エンジニアの鷹の目くんも、俺がソロをやり始めてから、ずっとレコーディングをお願いしていて、音的な部分で一番分かってくれてる人なので、そういう意味で今回は顔を見て話せる人だけで作り上げたアルバムなんですよね。
— そして、アルバムでは、1曲目から「実にドラマチックな街、TKD」って歌っていますけど、ドラマがない街のドラマというのは?
Campanella:環境も背景もドラマチックじゃない、何も生まれるわけがない街で、こうやって今、俺がラップ出来るところがドラマチックっていう、そういう感覚で書きました。
— つまり、Campanellaの頭の中がドラマチックであり、ありふれた日常がラップによって、ドラマチックになりえる、と。桃花台に戻る前に住んでいた名古屋と比べて、環境が作品に与えた影響はいかがですか?
Campanella:まぁ、名古屋だったら、遊び場もスタジオも近くて楽だったと思いますけど、名古屋もそこまでスピード感がある街じゃないし(笑)、桃花台まで30分で帰れちゃいますからね。ラッパーって、思っていなくても、勢いで書いちゃったりすることもあると思うんですけど、地元で無理せず書いたからこそ、今回のこういうアルバムが出来たので、結果的にこのタイミングで桃花台にいたのは良かったなって思いますね。今回のインタビューでは、もちろん、名古屋やTOKAIのことを聞いてくれて、それはそれでうれしいことなんですけど、自分としては、それよりももっと狭い、桃花台のコミュニティから生まれたアルバムなんですよね。そういう作品を東京のSPACE SHOWERっていうレーベルから大々的にリリース出来ることがうれしいですし、ここ最近、色々リリースされているコミュニティミュージックだったり、クルーのアルバムよりももっと狭くて密度が濃くて、一本筋が通ったクオリティが高い作品を作り上げられたことに、自分としては満足がいってるし、自信があります。
— しかも、このアルバムは閉じたコミュニティミュージックではなく、風通しがいいし、誰もが日常的にコミッット出来る、そんな世界が描かれていますよね。
Campanella:インタビューでは、原点回帰的に仲間と作りたくなった作品と捉えられたりもするんですけど、そういうことではないし、地元の誰かについていって、みんなが束になって同じようなことを歌ってアガっていこうぜっていうアルバムでもなくて。この作品は、もちろん、RamzaとFree Babyroniaは俺のことを多少は考えてくれているんでしょうけど、それぞれが作りたいものを自由に作って、その良さを最大限に活かした作品であって、地元をホントの意味でアゲるなら、クオリティが突出した作品を広く届けることをやらないとダメだなって。だから、自分にとっては、このアルバムこそが真のコミュニティミュージックだと思ってます。
Ramza:自分のビートは、ホント好きにやったというか、「よし分かった。がんばるよ」っていうような協力的なスタンスではないというか、自分のペースは一切曲げなかったですね。だから、Campanellaも途中で諦めてたと思います。やり取りに関しては、僕が日々作ってトラックを聴きに来て、あいつの肌に合うものを持っていくっていういつものスタイルなんですけど、僕が作ったくせに「えぇ、このダサいの持ってくんすか~」ってごねたりして(笑)。このアルバムは、自分が納得出来るビートしか渡さなかったですね。
Free Babyronia:僕の場合、やり取りはすごくシンプルで、「トラックが欲しい」と言われて、それを受けて、曲が作り始めて、完成したら、渡すっていう。細かいやり取りは特になかったですね。ただ「Birds」に関しては、自分が4月にリリースしたアルバム『Komaki』に入れた曲だったので、「ラップを乗せるなら、こういう感じがいい」っていうようなやりとりを少ししました。
— 『Komaki』は、Free Babyroniaの他の作品と比べると、ビートに寄った作品という印象を受けました。
Free Babyronia:おっしゃる通り、『Komaki』はビートに寄った曲を選んでまとめたアルバムなんです。カセットテープでのリリースを念頭に、曲を選んで少し手を加えて作ったものなんですけど、音源の多くは結構前に作ったものです。そして、完成したテープをCampanellaに渡したら、チリの詩人、パブロ・ネルーダの同名の作品に触発されて生まれた「Birds」を使いたいって言ってきたので、ラップが乗るようにリエディットしました。

Free Babyronia『Komaki』
前作『Matrix Grooves』から3年ぶりとなる2016年のセカンド作。日常の風景をノイズ、アンビエントの繊細なテクスチャーとマッドなビートに変換した危うくも美しい音楽世界が(高音質音源)ダウンロードコード封入のカセットテープという異なる音質のメディアから響き、描かれる作品だ。
— 色んなビートメイカーがトラックを提供したショーケース的な前作『VIVID』とRamza、Free Babyroniaと作り上げた今回のアルバムでは、音楽に対する向き合い方はどう違いましたか?
Campanella:確かに『VIVID』は、これもやれる、あれもやれるっていうアプローチで、ショーケース的なアルバムだと受け取られるのはよく分かるんですけど、ラップについて言えば、俺は一つのことを簡潔に、ストレートに伝えるのが好きではなく、言葉遊びを大事にしていて、『PEASTA』では、その遊び方が変わった感じ。気持ちのアゲ方を例えるなら、ビールを飲み続けているのが『VIVID』で、ワインや焼酎だったり、その時の気分で飲む酒を変えているのが『PEASTA』ですね。今回の取材では、心境の変化について聞かれることが多いんですけど、心境の変化はもちろんあるにせよ、酒を飲み続けていることには変わらないし、違いといっても、それくらいのものなんですよ。
Ramza:ビートメイカーの視点でいうと、近い距離にいる3人が1曲ずつ作っていったら、自然とアルバムにまとまったという感じなんですよね。作ってる途中、「これ、まとまらないだろうな」って思ってたんですけど、なんか出来ちゃいましたよね。しかも、オーセンティックなものがもてはやされている時代に近年稀に見るようなオルタナティヴなヒップホップ作品が出来ましたね。

Campanella『VIVID』
2011年のフリーダウンロード・アルバム『DETOX』を経て、2013年にリリースされたソロ・ファースト作。盟友RamzaとTOSHI蝮、ILLCIT TSUBOIほか、BUSHMIND、DJ HIGHSCHOOL、Fla$hBackSの3人やOMSBらが参加。スキルフルなラップが直線的にテンションを高めながら、多彩なビートを乗りこなす。
— アルバムのリリックは、リスナーに解釈が委ねられている部分も多いと思うんですけど、bal 2016 AWイメージ・ムーヴィーにインストが使われている5曲目の「KILLEME」は、鋭利な言葉でメッセージが刻まれていますよね。
Campanella:人間は矛盾した生き物だと思うので、その矛盾点をいちいちあげつらうつもりはないんですけど、他のことはよくても、それを言っちゃうのはどうなの?って思ったことをそのまま書いただけなんですけどね。
— あのエクストリームなトラックはどのように生まれたんですか?
Free Babyronia:実はフリースタイルでラップしながら、あのトラックを作ったんですよ(笑)。最初の段階から、極力、ラップを生かしたトラックが作りたかったし、生かすも殺すもラップ次第って感じのシンプルでタフなものを作ったつもりです。それに対して、Campanellaが「こういうことだよね?」って感じでうまいことやってくれたと思います。
— 「KILLEME」はとりわけ濃密なものがありますけど、日常を歌った他の曲のラップからもRC SLUMの流れを汲む、張り詰めたテンションと渦巻く熱量を感じました。
Campanella:今回のトラックから受けるであろう印象とは結びつかないかもしれないですけど、90年代のラッパーの唾が飛んでくるような勢いや熱量をどこかで感じ取ってもらえたらうれしいですし、自分としてはそういうつもりでラップしているんですけどね。
— ATOSONE主催のパーティ「METHODMOTEL」に行くと、出演者は毎回顔を合わせているはずなのに、決してユルくならないというか、いい意味での緊張感や強いエネルギーが感じられるんですよ。
Campanella:そうですね。みんな、個として成り立たせようとしているし、あのパーティではそういう気持ちを特に際立たせようとしてますからね。RCのみんなは自分が一番格好いいと内心思って、ライヴやってるんじゃないかな。
— 6曲目の「Shoo-in」にフィーチャーしているTOKAIのラッパー、NERO IMAIもC.O.S.A.もマイクを握った瞬間から場を支配出来る、素晴らしいラッパーですもんね。
Campanella:そうですね。俺のなかで、いま日本で一番ラップが上手いのはNEROくんだと思っているし、フックを歌ってもらったのは、そのパートを自分でも歌いたいなって思ったから。C.O.S.A.は高校生の頃から知ってて、COSAPANELLAとして一緒に作品も出しているんですけど、そのことを抜きにしても、あいつのヴァースを聴きたいと思ったんです。俺は考えたこと、起きたことをそのままにしか書けないんですけど、C.O.S.A.は実際に起きたことを2倍にも3倍にもドラマチックに描写する表現力が突出してますからね。
— 考えたこと、起きたことをそのまま書いているのに、Campanellaのラップがエモーショナルに響く秘密というのは?
Campanella:どうしてなんでしょうね? アルバムのラスト曲「outro」のラップはほぼ一発録りで、面倒臭いことがあったり、深刻な意味ではなく、不安定な、調子が良くない瞬間を経た曲で、2015年1月に「Cold Draft」という曲名で配信リリースしたんですけど、今回のアルバムは、あの曲に引っ張られて、作品全体のトーンが決まったところもあったんですよね。自分としては、楽しいことだけを歌いたいという気持ちももちろんあったんですけど、それは今の自分にとってリアルじゃないなって思ったし、そう思いつつも、今回の作品が最終的には自分のなかでアガれる作品になったことはうれしかったですね。
— Ramzaから見て、Campanellaはどんなラッパーですか?
Ramza:高1の頃から僕とFree Babyroniaは隣でラップしてたし、その頃からC.O.S.A.やTOSHI(蝮)くんだったり、周りのみんなのラップは知ってましたけど、僕のなかでは当時からCampanellaのラップは頭ひとつ抜けてたかな。リズム感や発声の仕方……声に倍音が多く含まれてて、ライヴでもデカい声を出さなくても通ったりするし、ビートに言葉をぶつけるアプローチに関して、Campanellaなりの方法やマジックを持っているような気がしますね。
— 倍音ですか。ビートメイカーらしい面白い視点ですね。
Ramza:倍音だったら、TOSHI蝮ですよ。あと、5lackかな。まぁ、でも、活躍しているラッパーは何かしらいい声してますよね。
— そして、RamzaとFree Babyroniaが手掛けたビートに関しては、アメリカの最新トレンドをただ輸入したという意味の新しさではなく、独自に切り開いたビートの斬新さは本当に刺激的だし、最高だと思います。
Campanella:トラップは今後もまだ続くと思うんですけど、もはや、そこには新しさが全くないじゃないですか。それに対して、このアルバムは俺のラップがどうこうということではなく、1年後も2年後も3年後もずっと新しいと思うんですよ。
— Ramzaは2年前に限定リリースしたビート集『Dusty』で某シューゲイザーバンドの曲をチョップして使っていたし、Campyが2011年に出したフリーのミックステープでレディオヘッドの曲にラップを乗せてたり、ヒップホップ、ブラックミュージック以外の音楽も3人の滋養になっていますよね。
Ramza:そうですね。10代の頃は聴いている音楽をほとんどシェアしてきて、好きな音楽は似ていると思うけど、なぜか上手いこと個性に繋がりましたよね(笑)。3人でラップしてた時もオーセンティックなビートから逸脱してたし、それがクールだと思ってましたからね。
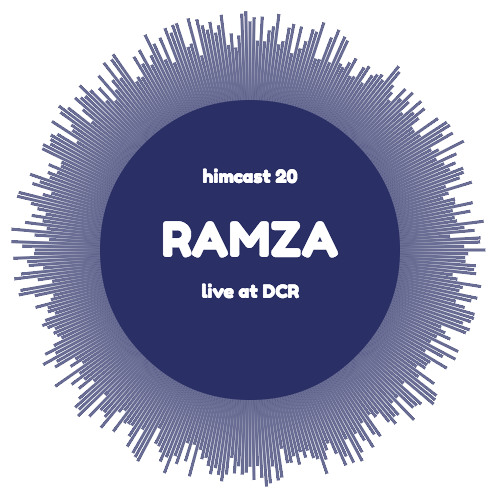
Ramza『Machine Live at DCR himcast 2013-12-21』
2011年発表のフリーダウンロード作品『GERALD』、2014年のストリート作品『DUSTY』を経て、ファーストアルバムが完成間近のRamza。SP-404を使用した2013年末のディープなマシーン・ライヴ音源。
Campanella:一時期、ヒップホップを聴いてない時期もあって、その頃はFree Babyroniaとシガー・ロスだったり、当時、誰も知らないようなアイスランドのエレクトロニカを深掘りしてたんですけど、その頃、Ramzaは90年代のヒップホップだったり、独自にあれこれ聴いていて、3人で週3くらいで集まってはこれが良かった、あれが良かったってやってて。
Ramza:当時、ケンカしましたからね。俺はブラックミュージックにスピリチュアルなものを感じて、好き好んで聴いていたんですけど、一方、CampanellaとFree Babyroniaはアイスランド音楽のスピリチュアルな部分にハマってて、その対立。スピリチュアル戦争でしたよ(笑)。
Campanella:でも、そうこうするうちに、RamzaがFlying Lotusのファーストを持ってきて、そこが3人の接点になったし、彼らはその後も独自に音楽探究し続けて、その成果がオリジナルな作風に昇華されているんだと思いますね。
Ramza:その頃の現行のブラックミュージックにはスピリチュアルな感覚があまり見当たらなくて、僕は彼らのすすめで彼岸の音楽みたいのばっか聴いてたんですけど、Flying Lotusは精神的な面でまとまらなかった点を一つにしてくれたという印象ですね。
RamzaのRaは太陽神ラーのことなんですけど、つまりはそういう精神的な部分を再度刺激されたということなんですよ。

Flying Lotus『1983』
2006年に西海岸の名門レーベル、プラグ・リサーチよりリリースされたファースト作。
叔父であるジャスサックス奏者、ジョン・コルトレーンのスピリチュアリティを継承したコズミックかつエレクトリックなビートが展開されている。
— 太陽神ラー、つまり、Sun Raですね。
Ramza:そう。今でこそ、ブラックミュージックのスピリチュアリティにはそこまでこだわっていないんですけど、昔はかなり傾倒してたんですよね。でも、今は誰も聴いたことのないようなヒップホップを作りたいと思ってます。例えば、何かの拍子にピンク・フロイドを聴くと、「スゴいの作ってるな。これ、40年前のアルバムだぞ」って思うし、一過性の作品には目もくれず、自分の音楽もそうありたいなって。とはいえ、それは、自分の音楽でシーンを変えたいとか、そういう大それたことじゃなく、これまで自分が色んな音楽を聴いて、衝撃を受けたり、エモーショナルな体験をしてきたように、単純にただそれを自分の音楽によって繰り返したいだけなんですけどね。
— RamzaとFree Babyroniaはエキシビジョンを行ったり、アートに傾倒しているという共通点もありますが、色んなラッパーにビートを提供しているRamzaに対して、Free Babyroniaは、2013年のファースト作『Matrix Groove』や今年出たセカンド作『Komaki』を聴く限り、ビートミュージックというより、サウンドアートに近い気がします。
Campanella:そうですね。2人ともすごく才能があって、Ramzaは「自分がやってることはヒップホップだ」って言ってるし、Free Babyroniaに関しては、近いところにいる俺から見ても謎な部分が多いんですけど、ひさしぶりにビートを鳴らしても、出音が他とは全然違うし、やっぱり、Free Babyroniaはヒップホップだなって。ただ、俺から見た2人はビートメイカーというより、音楽家であり、アーティストという印象ですね。
— Ramzaのアウトプットは、自分としてはヒップホップだと捉えてる?
Ramza:そうですね。バカみたいにこだわっているわけではないんですけど、僕はずっとヒップホップをやってるつもりですね。使ってる言語はヒップホップだけど、何をしゃべるかは自由って感覚かな。ヒップホップって、「どうだ!カッコイイだろ!」っていう性格の音楽じゃないですか。僕はヒップホップのそういうところが好きなんですね。
— Free Babyroniaにとっては?
Free Babyronia:自分のなかで、ヒップホップは、コア、心臓みたいなものですね。ただ、自分は作るものに一貫性がなく、分裂しててまとまりがないんですよ。だから色んな名義で音源を出してるし。自分としては特に何かを意識せず好きなようにやってます。
— どういったインスピレーションをもとに曲を作ることが多いですか?
Free Babyronia:課題やテーマは曲によって、あったりなかったりするんですけど、自分としては、和音や構成、グルーヴやテーマだったり、色んな要素に価値を置いていますし、音質や音響に関しては自然とセンシティヴになりますね。音質や音響とひと口に言っても、数学的な音響作品や一流スタジオで録られた音も大好きですし、おもちゃのマイクを使ってテープに多重録音したような超ローファイな質感や空気も好きなんです。制作の際には、とても細かい音や倍音、ノイズや空気、音質や音響のディテールで曲の印象がガラッと変わることもあるし、音質や音響は、そうやって無意識下の言語化できない感受性を刺激することのできる面白い要素だと思ってますね。
— ちなみに、今回のアルバム告知には、ビートメイカーにD.O.I.さんの名前も挙がってたじゃないですか。恐らくは、D.O.I. feat. TOKONA-X「EQUIS.EX.X」の流れを踏まえてのオファーだったと思うんですけど、『PEASTA』は、当時、D.O.I.さんがソロやINDOPEPSYCHICSで切り開いビートミュージック、エレクトロニカのさらにその先にある作品として捉えることも出来るかと。
Campanella:D.O.I.とTOKONA-Xのあの曲は、カッティングエッジなトラックにあんなにワルいラップが乗っていて、当時ホントに刺激的だったんですよ。だからこそ、D.O.I.さんにビートを提供していただいたんですけど、残念なことに『PEASTA』にはどうしてもハマらなくて。
Ramza:でも、僕はINDOPEPSYCHICSが好きだったし、ある意味、その子供だと思っているので、そう言ってもらえてうれしいです。彼らがJan Jelinekとやった「Moxa」とかマジでヤバいし、ホント好きなんですけど、比較されるのは恐れ多いです。

INDOPEPSYCHICS『INFINITE IN ALL DIRECTIONS』
90年代後半から00年代初頭にかけて、ビートミュージックのフロンティアを開拓したDJ Kensei、nik、D.O.I.からなるプロダクション・チームが2011年にリリースしたベストアルバム。リマスタリングは、LAビートシーンの看板パーティ、Low End Theoryを主宰するDaddy Kevが担当した。
— D.O.I.さんとの共演は実現しませんでしたが、そういう挑戦的な姿勢が作品をスリリングなものにしていると思います。
Campanella:Ramzaのトラックでずっとラップしてきて、「Campanellaのラップが乗ったことで、初めて、トラックの拍が取れた」って、よく言われるんですよ。INDOPE以降のエレクトロニカ・ヒップホップは、ヒップホップの枠組みをどんどん逸脱していきましたけど、そういうラップが乗らなそうなトラックに自分はラップを乗せてみたいし、チャレンジングな姿勢で臨んだこのアルバムもヒップホップリスナーだけでなく、幅広い音楽好きに届いたらうれしいですね。
— Ramzaは、フリーダウンロードの『GERALD』やストリート・リリースの『Dusty』といった作品をこれまで発表してきましたが、いよいよ、正規のファースト作がリリースされるとか?
Ramza:気づいたら、自分のアルバムを出さないまま、かなりの時間が経っちゃってて、何年もの間、色んな人から出せ出せ言われていたんですけど、ようやく目処が立ったので、いよいよ出せそうです。まぁ、期待しててください。
— では、最後にRamzaが提供してくれたミックスについて一言お願いします。
Ramza:最初は某現代音楽家縛りのミックスを作ってたんですけど、友達にふざけ過ぎと言われたので、ヒップホップのミックスを新たに作りはじめて、最終的にヒップホップかどうか分からないミックスが出来上がりました。テーマは特にないんですけど、自分の感覚として、どこか一線で同じ匂いがする内容、耳触りやノリが好きな曲を集めた雑なミックス……まぁ、でも、僕がきっちりやってもしょうがないんで(笑)、そういう部分込みで楽しんでもらえたらうれしいです。